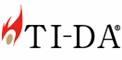ブログを初めて3年8ヵ月、FacebookやTwitterを初めてもうすぐ2年になるが、あいかわらずのWebオンチ機械オンチの症状は続いていて、操作ミスもよく起こる。
本日の夜明け前、今こうして書き直している新しい記事が冒頭部分を書いたばかりのところで何故か公開されてしまい、慌てて削除しようとしたところ、「管理画面」で記事二つ分の削除ボタンを押してしまったようである。どうしてそうなったかわからないが、わたしの場合、こういうことは時々起こる。
削除してしまって、それからなんとか再アップすることができた5日前のエントリーは、
『作家・池澤夏樹氏のこのコラムは全国民必読。「沖縄、根拠なき負担」』である。→
http://watanatsu.ti-da.net/e4359004.html
再投稿した記事には朝方お詫びを添えさせていただいたが、2月11日午前6時頃の時点で、この記事には4000を超えるアクセスがあり、ツイートされた回数は120回、「いいね!」ボタンを押してくれたFacebook利用者は1900人を超えていた。それだけの方たちの「拡散」してくださった「痕跡」まで消してしまった形になり、大変申し訳ないことをしたと思う。ご寛容くだされば幸いである。
*
本題に入る前に、いま少し前置きにお付き合いください。
ネット上の情報伝達やコミュニケーションは非常に難しいよなぁ、というお話である。
WEBオンチがWEBに親しみ始めたのは、沖縄に引っ越した2006年以後のことである。それまではほとんどパソコンを触ったこともなかった。しかし、東京の親しい編集者たちから、「渡瀬さんが使っている旧式のワープロのフロッピーを郵送で送ってもらったとしても、こちらに着くには時間がかかります。締切に間に合うか心配です。パソコンのメールでの原稿のやりとりを覚えてください。そうでないと、仕事を頼みにくくなりますよ」と脅されて、しぶしぶパソコンを触り始めた次第である。
そんなわたしが、見様見真似で「てぃーだブログ」にブログを開設したのが2009年の5月末。ツイッターとフェイスブックを始めたのが、さらに2年ほど後のことである。WEBオンチを自他ともに認めるわたしが、三つとも、誰の力も借りずに自力のみでスタートできているのは、われながら奇跡に近いことだったと思う。俺ってもしかして機械オンチではないかもしれないと錯覚したこともあったが、いやいや、しょっちゅう原因不明のパソコントラブルに見舞われたり、原因不明の「記事消失」に苛まれるなどしてきている。どれひとつとして原因が理解できたためしがない。
慣れればなんとかなるだろうという読みは甘かった。いずれにしても、ブログ、ツイッター、フェイスブックに関しては、不安を抱えたままのユーザーであり続けている。
ブログとツイッターとフェイスブックの性格の違いについても、最近になって、すこーしわかったきたかなぁ、というレベル。
現時点で理解できたことは、わたしはツイッターでの短文のキャッチボールや、あるいはフェイスブックのコメント欄のやり取りによるコミュニケーションでさえ、大の苦手だということ。不向きだということ。たったひとつの出来事に関する思いを伝える場合でさえ、一定の長さをもった文章を書きたくなる。何かしらの質問や批判に対しては、相応の字数を費やして、じっくり応えたくなってしまうのである。
殊に最近ではこう痛感するようになっている。ツイッターの140字以内という制限のもとで意見交換しろと言われても、言いたいことを伝えきれる自信がまるでない。だからこのところは、新聞記事、ブログ記事、動画などを、一人でも多くの人に紹介したいと思ったとき、あるいは単純にその時の感情を不特定の友人に向かってつぶやきたくなったとき、さらには目撃した情報をその場でいち早く伝えたいとき、そんなときに、ツイッターを使っている。そういう利用法しかできず、あしからず、という気持ちに傾いている。誰かのツイートに思わずこちらから絡んで「しまった」と後悔することも未だにあるが、それは自業自得なので相手の気のすむ区切りまでキャッチボールをしてから退散したりもする。慣れればなんとかなるかと言えば、やはりまるで慣れそうにはない。
単行本にしろ雑誌にしろ、出版メディアの中での発言は、曲がりなりにも生業ということもあり、字数制限に従うのは当然と自覚している。だがそれでも、紙数の許す限りギリギリまで言葉を尽くしたいと考えてしまう。もっとも書きすぎた場合は、担当編集者がきちんと指摘してくれるので、こんなわたしであっても、大きな問題が起こったことはこれまでには皆無である(小さな問題発生は…日常茶飯…苦笑)。
従って、わたしをツイッターでフォローしてくださっている奇特な方、あるいはFacebook友達になってくださっている方にとっては、渡瀬って、議論のし甲斐のないやつだなぁと思われる場合もあるかもしれない。そこで、なにかツッコんだコミュニケーションが必要な場合は、なるべくダイレクトメッセージやメールを使ってご連絡をくだされば幸い。
公の場でのやり取りが必要な場合は、例えば往復書簡とか、ある程度長い文章を書かせていただける環境をつくってくださることを望みます。勝手な要望とは存じますが、ゆたさるぐとぅうにげーさびら(よろしくお願いいたします)。
あるいは名指しでしっかりとご批判下さる場合には、当方も当ブログなどでしっかりとお応えしたいと思います。
*
ようやく本題である。
このたび池澤夏樹さんのコラムを当ブログで全文紹介して、本当によかったと思っている。
わたしが一人でも二人でも、この紹介によって目にする人が増えてほしい、と願った以上にたくさんの方が読んで、共感してくださった。
沖縄で全国紙を定期購読している人は極めて少ない(わたしも図書館で時々チェックする程度だ)。だから、沖縄の友人にも知ってほしいという気持ちが働いたのと同時に、じつはわたしの気づいた時点でのFacebookでの注目のされ方が、「ある部分」に偏ってしまっている危うさも感じた。
「ある部分」だけ注目されてしまっているという危惧の原因は、池澤さんが「縁起でもないことを敢えて言う」との断りつきで書いた最後の部分のみが、Facebook上で話題になっていたこと。
全体で115行のコラムのうちの最後の部分の14行だけが切り取られて、Facebookにアップされているのに気付いたのである。そこだけを見て先入観をもてば、池澤夏樹はとんでもない間違いを書く作家だ、ということになりかねない。これについては、後述する。
そうして、わたしは2月6日の午後、朝日新聞の置いてある某所へ走り、全文を確認したわけだが、その結果、池澤さん、よくぞ書いてくれた、という思いのほうが大きくなった。
ヤマト(沖縄以外の日本)に住む友人に対して、日頃目にすることの滅多にない「海兵隊に関する事実」がここに書かれているぞと知らせたい、という思いが強くなったのである。朝日新聞は、読売新聞に次いで部数の多い全国紙だが、夕刊の文化面までいつも見落とさずに読む人がどれだけいるのかはわからない。わたしの友人たちにはわたしのブログで知らせるのがいちばん早いのだ。
そうして、ブログで全文引用紹介した結果、直接間接にわたしに寄せられたメッセージは、ほとんどすべてが肯定的なものだった。
Facebook友達のメッセージのみならず、見ず知らずの読者からの声もたくさん届いた。
ヤマト(日本本土)のメディアも多くの作家も書かなかった大切なことを、よくぞ書いてくれた、という感想が最も多かった。
知らないことを書いてくれてありがとう、あるいは、言いたかったことを代弁してくれてありがとう、という意味の感謝の声も目立った。
お断りしておくが、ヤマトンチュの読者でなく、ウチナーンチュの読者からの感謝の声のほうが多かった。
海兵隊って、沖縄にいる必要がないんだ、って、わかってよかった。
そんな素朴な感想も寄せられた。
だだし、Facebookやブログなどで、複数の方が厳しい声を突き付けていることにも気づいたので、そのことにも触れないわけにはいかない。
作家のコラムの文責はご本人にある。わたしの出る幕ではない。解説しすぎるのは野暮だと思う。
ただ、わたしが気づいて、納得できた「間違い」の指摘については、このコラムを推薦した者としての責任において、ここに紹介しておきたいと思う。
最後の14行の冒頭、このブログに引用するとわずか7行の部分だが、「縁起でもないことを敢えて言う」に続く部分。
《縁起でもないことを敢えて言う。
二〇〇四年八月の沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事件で米軍はまこと横暴にふるまったが、幸いこの事故では住民への被害はなかった。今もしオスプレイが墜(お)ちて、もし一九五九年の宮森小学校米軍機墜落事件のようにたくさん死者が出たら(小学生十一人、一般住民六人)、抗議する沖縄人は基地になだれ込むだろう。米兵は彼らを撃つかもしれない。
小説家が大げさなことを言っていると笑ってほしい。しかしこの恐ろしい妄想には現実的な土台があるのだ。》
その中のこの部分。
《二〇〇四年八月の沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事件で米軍はまこと横暴にふるまったが、幸いこの事故では住民への被害はなかった。》
「幸いこの事故では住民への被害はなかった」という書き方はまずい。これは明らかな間違いだ、と憤る方の気持ちは充分にわかる。せめて「この事故では死者は出なかった」と書き直すべきだろうと思う。仮にわたしが編集者であれば、そう進言する。沖縄県民ならほとんどの人が、死者こそ出ていないものの、甚大なる被害が、精神的にも物理的にももたらされたことを知っているのだから。そして、その事実をほとんど報じなかった全国メディアの側の「犯罪的な呑気さ」も、わたしたちは知っているのだから。
だが、少し待ってほしい。
このことをもって、池澤夏樹という作家を全否定してはいけないと思う。
残りの100行に書かれていることは、多くの人が共有すべき、とても大事な、事実認識の「土台」である。
そのことをここまできちんと書けるヤマトンチュの作家は、皆無とは言わぬまでも、そうはいない。
その意義と価値をまずは認めつつ、細部への批判をしていただきたい、と願う。
膨大な小説、評論、随筆、詩などの作品を残してきている実績ある作家といえども、完璧な人間ではないはずだ。
あなたとわたしと同じように、日々の生活の中で些細な事に悩まされたりストレスを感じながら生き延びている人かもしれない。
沖縄にとっての「味方」を(完璧な味方でなくたって、カッコ付きの味方だってよいではないか、という意味をこめた表記だが)、敵にしてしまうことは、もったいなさすぎる。悲しすぎる。敵は、別のところにいるんだよ!! そう声を大にして叫びたくなる。
だいぶ長くなったが、まだ続きを書きたい。またしかし、余り長すぎるのも迷惑かもしれない(ブログの場合、編集者が介在しないので、自分でその役目も務めねばならない)。ともかく稿を改めたいと思う。
その上で、ひと言付け加えよう。
池澤さんには、1990年代に何度か(何度もという言い方もできなくはない)沖縄でお会いしている。池澤さんはその時期沖縄県民で、わたしは東京からの通いの者だった。最後に会ったのは、インタビューに応じてもらった1997年の大晦日のことである。
その印象と実感を込めて、はっきりと書いておく。
池澤夏樹さんは、謙虚で誠実な人物である。思慮深さに溢れた人でもある。戦争を憎み、市井の人びとの静かな暮らしぶりを尊び、自然の豊かさをこよなく愛する人。旅人としての目線からではあるだろうが、沖縄を心から愛していた。いや、今も愛しているはずの人。だからといって完璧な人なのでもないし、全肯定せよ、と言っているわけでもない。いたずらっぽさやそそっかしさや不器用さも、抱え込んで生きているのかもしれない。いずれにせよ、真摯な態度での批判の声は、作家は常に真摯に受け止めるべきだとも思う。
だが、最後の14行の部分、先入観と悪意をもって読んでしまうと、もしかしたらこの作家が「沖縄人が基地になだれ込んで撃たれるべき存在」と思っている、などと誤解することになってしまうのだろうか。
その極端な「読解の仕方」をわたしは肯定するわけにはいかない。15年前の池澤さんの謙虚さも、誠実さも、思慮深さも、いま変わり果ててしまったなどとは到底思わない。
最後の14行も、思慮深い池澤さんから発せられた、沖縄の訴えを、米軍駐留の理不尽さを無視し続けている「ヤマトンチュ」に向けた警告の表現だと、わたしは感じている。
もうひとつ、「沖縄人」という表現に激しい不快感を表明するウチナーンチュもおられるのだが、相反するわたしの実感をやはり、はっきりと記しておきたい。わたしが親しくさせてもらっているウチナーンチュの友人知人のなかには、むしろ「沖縄人」という言葉を積極的な意味で遣う人がいる。「沖縄人としての誇り」をこめてこの言葉を遣う人が身近に複数いる。沖縄人をオキナワジンと読むかウチナーンチュと読むかも、人それぞれである。
同様に、池澤さんの遣った「沖縄人」には、「沖縄以外に住む呑気で残酷な日本人」に厳しく対峙せざるを得ない人びとに対する敬意がこめられていると、わたしは感ずる。どうなってもいい存在として突き放しているなどとは、逆立ちしても読むことができない。「縁起でもないことを敢えて言う」という前置きの言葉は、字義通りに受け止めるべきだと思う。
くどいようだが、本稿の最後にもう一度書く。海兵隊の持つ意味、沖縄に駐留する根拠のないこと、そして、沖縄県民があらゆる正当な手段を駆使して、普天間基地の県外移設やオスプレイ配備の撤回を求めてきたという「沖縄の真実」を、ありのままにとらえ、そして伝えることのできないヤマトのメディア人や作家たち(不勉強であると差別主義者であるとを問わず)の多い状況にあって、いま作家・池澤夏樹氏が書いたことの意義と価値を、まずは認めたいのである。
(この項、もう少しつづく)