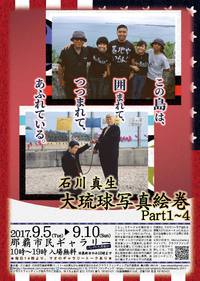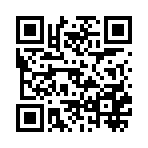2010年05月26日
県外の皆さん、琉球新報の昨日の社説、必見です!!

昨日の琉球新報の社説は、ぜひとも県外の皆さんにも読んでいただきたい。
琉球新報・2010年5月25日・社説
[普天間と振興策/アメとムチもはや通じず 経済発展阻むのは基地]
→http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-162577-storytopic-11.html
(以下、全文引用)
*
来県した鳩山由紀夫首相と懇談した県経済団体会議が、経済状況の報告を拒否した。首相の思惑に肩すかしを食らわせた格好だ。
首相は、沖縄側から「県経済の状況は厳しい」と言ってもらい、さも沖縄の願いを受け止めたかのように装って、振興に取り組む姿勢を示すつもりだったはずだ。そしてその映像を全国に流し、「沖縄は実は基地を望んでおり、県内移設はそう悪い話ではない」という誤った印象を国民に植え付けたかったのだろう。
経済団体側はその思惑を察知した。知念栄治議長は冒頭、「経済問題を話し合う環境ではなさそうだ」と述べて、基地と振興策とのリンク論をけん制した。
◆優れた判断
国民向けの印象操作で、経済団体側が政府より一枚上手だった形だ。優れた判断と言える。「県民の危険や苦労を売り渡すような野卑な団体には成り下がりたくない」(呉屋守将県建設産業団体連合会長)といった発言に、喝采(かっさい)を送った県民は少なくないだろう。
政府はこれで思い知ったはずだ。アメとムチを振りかざす一昔前の手法は、もはや県民に通用しないということを。それにしても、振興策をちらつかせれば途端に沖縄はなびく、と政府がいまだに見ていたことには驚く。1月の名護市長選でその手法が効果を失ったのは明らかだったはずだ。過去の出来事から教訓を導く能力が、彼らには決定的に欠けている。
政府の言う「振興策」は地域を振興などしなかった。北部振興策は市町村財政を極端な国依存型にしたにすぎず、名護市の失業率は10年前に比べむしろ悪化した。
市民はもう「振興策」の幻想性に気づいている。姑息(こそく)な工作にもはや効果はない。直ちにやめた方が政府のためだ。
問題は、考え方を改めるべきなのは政府だけではないということだ。沖縄経済は基地がなければ成り立たない、経済のためにいずれは受け入れる、という誤った見方が今も国民の間に根強くある。それを払拭(ふっしょく)しなければならない。
沖縄経済が一時期、基地に大きく依存していたのは確かだ。1950年代には基地関連収入が県民総生産の50%を超えていた。復帰時点で15・5%だ。だがその割合は年々減り、2007年は5・3%にすぎない。
基地は県土全体の10・2%、沖縄本島の18・4%を占める。それが5%程度の「稼ぎ」しかないのでは、効率が著しく低い土地の使い方と言うほかない。
基地であるより返還した方が経済効果が大きいのは、返還跡地を見ても明らかだ。那覇新都心の生産誘発額は返還前の16倍に上る。北谷町の美浜・ハンビーにいたっては215倍にはね上がった。
雇用の面でも、土地を民間に使わせた方がはるかに効果的だ。うるま市みどり町で働く人の数は、米軍天願通信所だったころに比べると293倍に増えた。那覇市の小禄金城地区でも12倍に上る。
◆機会損失は莫大
会計学に「機会損失」という概念がある。最善の行動を取らなかったために、利益を得る機会を逃してしまうことを言う。
基地と経済にもあてはまる概念だ。基地になった土地を、もし民間が使っていればどうだったか。
例えば普天間飛行場の基地収入と、基地の外の宜野湾市域の純生産を比べると、1ヘクタール当たりで基地の外が2・5倍も高い。浦添市のキャンプ・キンザーも同様だ。沖縄の膨大な基地面積を考えると、失われた生産額は莫(ばく)大(だい)だろう。
基地のために交通が阻害されてきた弊害も見逃せない。渋滞による経済コストも考えれば、機会損失はなお膨らむ。
富川盛武沖縄国際大学長は「土地や労働力の基地への投入が市場メカニズムにつながらず、経済の足かせになっている」と指摘している。基地が経済発展を阻んでいるのは火を見るより明らかだ。
経済のためにも基地は返還した方がよい。返還跡地の発展ぶりを見ているから、県民はそれを肌で知っている。今回の経済団体の行動も、その反映と言えよう。
だが本土には十分に伝わっていない。残念な事態だが、繰り返し沖縄の実態を説き、根気強く誤解を取り除くしかない。
言うまでもないが、基地の最大の弊害は事件・事故による人権の侵害だ。この社会的コストは「振興策」などで決して取り戻せないことも、肝に銘じたい。
(引用終了)
*
蛇足はなるべく控えたいが、東京滞在中のわたしは、この社説をネットでチェックする以前には、23日首相訪沖の際の事実をきちんと把握していなかった。首相が沖縄経済界の代表メンバーと会うという日程は知っていても、その経済界の代表たちが、毅然たる姿勢を首相・政府に対して示したという事実を、知らなかったわけである。
この社説に書かれているような、沖縄の経済団体の政府への対応は、非常に重要な事実であるにもかかわらず、本土メディアは伝えていない。洩れなく全メディアをチェックしたわけではないが、皆無に近かったはずだ。
社説の書き方から察するに、沖縄のテレビニュースなどでは、経済界の代表のコメントがお茶の間に流れたのであろうか。県民から喝采を送られたであろう経営者たちの言葉も、東京にいれば、まるで知らされないままだ。
以前から述べているように、「温度差」という生易しい言葉では済まされないぐらいの、沖縄と本土の間に横たわる深く大きな意識の溝を証明する、これも一例だろう。
県外の皆さん、毎度の話で恐縮ですが、琉球新報http://ryukyushimpo.jpも、沖縄タイムスhttp://www.okinawatimes.co.jpも、主要記事や社説は、ネットでも読めます。QAB琉球朝日放送http://www.qab.co.jp/、RBC琉球放送、OTV沖縄テレビ放送のローカル・ニュースも、一部はネットで視られます。
やはり皆さん、ぜひとも、沖縄のメディアが発する情報を、まめにチェックしてください。
よろしくお願いします。
琉球朝日放送開局15周年・報道特別番組「どうなる普天間移設」朝まで徹底生激論は、
こちらから→http://www.qab.co.jp/asanama/

Posted by watanatsu at 17:58
│時事問題