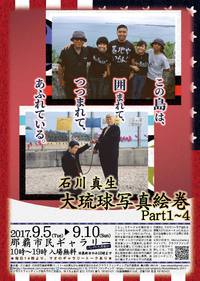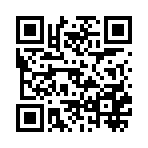2010年06月07日
内田樹氏にとっての「普天間問題」。
ふと思いついたのだが、当ブログにおいては、沖縄県民の目線による「普天間問題」リポートのほかに、これから時々は、世の識者、論客といわれる人々にとっての「普天間問題」を、わたしなりのやり方で紹介してみようかと思う。
過去にわたしが行ってきた、この新聞はペケだが、この新聞はマル、なんぞという紹介の仕方はあんまり意味がないように思えてきた。もちろん、当ブログ読者の皆さんに対しては(特に県外の皆さんには)、「沖縄の現実」は、沖縄タイムス、琉球新報など地元沖縄のメディアから読み取ってくださいというお願いだけは続けたい。しかし、それだけではじつに心もとないと思うようにもなっていた。
なぜそう思ったか? 二つの出来事が重なったのだ。
こと「普天間問題」に限ってみても、最近、新聞やテレビなど東京の大手メディアの「思考停止」状態には、ホトホトうんざりさせられ、あきれさせられることの連続だった。例をあげればキリのないほどの多さゆえ、ここで紹介したり批判する気力さえ湧かない。「普天間問題」の本質に少しも迫ろうとしない、アホなメディアの発する情報の洪水を日々浴びていると、深い徒労感ばかりが募る。これでは自分も含めて読者・視聴者の眼力は、知らず知らず衰えてしまう。という強い危惧を覚えていた。
そんなところへ、わたしが長年世話になり、信頼を寄せている雑誌編集者から、貴重なアドバイスがあった。ネット上には、こんな論客の、注目に値するブログ(複数のブログ!)もあるし、こんな発言も動画で見ることができるのだよ、と、(こういう言論がある限り世の中捨てたもんじゃないよ、という意を暗に込めて)懇切丁寧なアドバイスをくださったのだ。Nさん、ほんとにありがとうございました。
これがじつに、参考になった。と同時に、いまや、大手新聞・テレビにまともな言論を期待するのは間違いで、玉石混交のWEB情報世界に「玉」を探す旅に日々出ていくしかないのだろうか、とも思うのだった。その場合、WEBオンチのわたしには、当分ナビゲーターの存在が必要だよなぁと呟きつつ、しかし、「ネットメディアならではの言論」の今後の可能性、役割の重要性については、大真面目に考えされたのでもある。
さてNさんが教えてくれた、「玉」の一例は、思想家、エッセイストとして知られている内田樹(うちだ・たつる)・神戸女学院大学教授のブログであった。→「内田樹の研究室」http://blog.tatsuru.com/
読書家諸兄姉にはわらわれてしまうだろうが、わたしはベストセラーといわれている氏の著書を、まだどれひとつ手にしたことがなかった。しかし、ブログ記事のいくつかを読んだだけで、この人が、物事の本質をまっすぐ見極める鋭い眼差しと広い視野とある種の遊び心を、同時に兼ね備えた知識人だということは、すぐにわかった(いずれいくつか著書を読ませていただこうと思った)。
内田氏はそのブログで、「普天間問題」へも何度も論及しているのだが、メディアの側の頓珍漢ぶりをもスバリ指摘していて、小気味よい思いがしたものである。
いくつかの文章からわたしが把握した氏の考え方を、強引に簡略化して述べれば「日本はアメリカの軍事的属国である」という明らかな事実を認めずに、安全保障を語ることに意味はないし、その事実を認めなければ、「普天間問題」についてもまやかしの議論に終始して当然だ、ということになる。
ここで、誤解のないようにあらかじめ述べれば、氏は武道家でもあるが、しかし軍国主義者ではない。「憲法9条2項」をきちんと守れという主張をしている人だ。
まぁ、ともかく読んでいただくに限る。
たとえば、こんなブログ記事。
2010年5月7日付「基地問題再論」
→http://blog.tatsuru.com/2010/05/07_1708.php
2010年5月11日付「アメリカから見る普天間問題」
→http://blog.tatsuru.com/2010/05/11_1158.php
チャルマーズ・ジョンソン氏の発言を紹介している人がここにもいてくれたか、という感じである(わたしは「辺野古浜通信」http://henoko.ti-da.net/などでも知らされていた)。
ほかにも内田氏のブログには「普天間問題」についての論考がいくつもあるので、興味のある方は、ご自分で見つけてください。ただ、このブログは「超人気」らしく、アクセスがうまくいかないこともあります。その点はご注意を。
では本日も、良き一日になりますように。
過去にわたしが行ってきた、この新聞はペケだが、この新聞はマル、なんぞという紹介の仕方はあんまり意味がないように思えてきた。もちろん、当ブログ読者の皆さんに対しては(特に県外の皆さんには)、「沖縄の現実」は、沖縄タイムス、琉球新報など地元沖縄のメディアから読み取ってくださいというお願いだけは続けたい。しかし、それだけではじつに心もとないと思うようにもなっていた。
なぜそう思ったか? 二つの出来事が重なったのだ。
こと「普天間問題」に限ってみても、最近、新聞やテレビなど東京の大手メディアの「思考停止」状態には、ホトホトうんざりさせられ、あきれさせられることの連続だった。例をあげればキリのないほどの多さゆえ、ここで紹介したり批判する気力さえ湧かない。「普天間問題」の本質に少しも迫ろうとしない、アホなメディアの発する情報の洪水を日々浴びていると、深い徒労感ばかりが募る。これでは自分も含めて読者・視聴者の眼力は、知らず知らず衰えてしまう。という強い危惧を覚えていた。
そんなところへ、わたしが長年世話になり、信頼を寄せている雑誌編集者から、貴重なアドバイスがあった。ネット上には、こんな論客の、注目に値するブログ(複数のブログ!)もあるし、こんな発言も動画で見ることができるのだよ、と、(こういう言論がある限り世の中捨てたもんじゃないよ、という意を暗に込めて)懇切丁寧なアドバイスをくださったのだ。Nさん、ほんとにありがとうございました。
これがじつに、参考になった。と同時に、いまや、大手新聞・テレビにまともな言論を期待するのは間違いで、玉石混交のWEB情報世界に「玉」を探す旅に日々出ていくしかないのだろうか、とも思うのだった。その場合、WEBオンチのわたしには、当分ナビゲーターの存在が必要だよなぁと呟きつつ、しかし、「ネットメディアならではの言論」の今後の可能性、役割の重要性については、大真面目に考えされたのでもある。
さてNさんが教えてくれた、「玉」の一例は、思想家、エッセイストとして知られている内田樹(うちだ・たつる)・神戸女学院大学教授のブログであった。→「内田樹の研究室」http://blog.tatsuru.com/
読書家諸兄姉にはわらわれてしまうだろうが、わたしはベストセラーといわれている氏の著書を、まだどれひとつ手にしたことがなかった。しかし、ブログ記事のいくつかを読んだだけで、この人が、物事の本質をまっすぐ見極める鋭い眼差しと広い視野とある種の遊び心を、同時に兼ね備えた知識人だということは、すぐにわかった(いずれいくつか著書を読ませていただこうと思った)。
内田氏はそのブログで、「普天間問題」へも何度も論及しているのだが、メディアの側の頓珍漢ぶりをもスバリ指摘していて、小気味よい思いがしたものである。
いくつかの文章からわたしが把握した氏の考え方を、強引に簡略化して述べれば「日本はアメリカの軍事的属国である」という明らかな事実を認めずに、安全保障を語ることに意味はないし、その事実を認めなければ、「普天間問題」についてもまやかしの議論に終始して当然だ、ということになる。
ここで、誤解のないようにあらかじめ述べれば、氏は武道家でもあるが、しかし軍国主義者ではない。「憲法9条2項」をきちんと守れという主張をしている人だ。
まぁ、ともかく読んでいただくに限る。
たとえば、こんなブログ記事。
2010年5月7日付「基地問題再論」
→http://blog.tatsuru.com/2010/05/07_1708.php
2010年5月11日付「アメリカから見る普天間問題」
→http://blog.tatsuru.com/2010/05/11_1158.php
チャルマーズ・ジョンソン氏の発言を紹介している人がここにもいてくれたか、という感じである(わたしは「辺野古浜通信」http://henoko.ti-da.net/などでも知らされていた)。
ほかにも内田氏のブログには「普天間問題」についての論考がいくつもあるので、興味のある方は、ご自分で見つけてください。ただ、このブログは「超人気」らしく、アクセスがうまくいかないこともあります。その点はご注意を。
では本日も、良き一日になりますように。
Posted by watanatsu at 12:56
│ブログ論