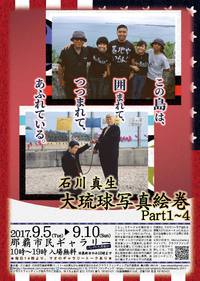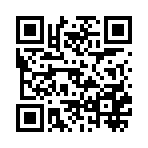2010年06月19日
極私的新聞解説・その2。東京新聞の場合。
東京新聞は、おそらく社の方針として定めた上であろうが、このところ積極的に「沖縄」関連のテーマで特集記事を組んでいる。
とくに「こちら特報部」は、基地問題、普天間問題にも切り込むことが多いので、注目している。しかしこの「特報」面はWEBでは読めない。沖縄に帰るときには、月額わずか105円払えば携帯電話で「特報」面などが読めるという、その契約を必ずしようと思っている。「辺野古浜通信」ブログの管理人さんは、東京新聞の愛読者なので、次のような紹介を時々してくれている。→http://henoko.ti-da.net/e2926927.html
その東京新聞が、6月14日、16日、17日の3回にわたり、社会面において「沖縄」特集記事を連載した。
通しタイトルは、
記憶 戦後65年
新聞記者が受け継ぐ戦争 沖縄戦「差別」の源流
というもので、上・中・下の3回にわけての記事であった。
社会部・佐藤直子・小嶋麻友美、と署名があるから、二人の記者の共同作業らしい。

「上」では、
基地の島 また「捨て石」
「第2の琉球処分」に怒り
との大見出しが掲げられている。
わたしは、記事を少し読み進んだところで、あっ、と小さな声をあげた。
沖縄戦時の座間味島での集団自決についての記述の中に、ブログ仲間でメル友で人生の先輩であるところの、「知人」の名前を発見したからだ。その部分を引用する。
《本島より一週間ほど早く、米軍の空襲を受けた慶良間諸島・座間味島でも、百三十人余の村人が避難していた壕で、手りゅう弾を使ったり肉親同士で手をかけたりして絶命した。当時四歳の宮里洋子さん(69)は「死ぬのいやー」と叫んで、かみそりを握った母から逃げた。だが、その記憶は宮里さんにはない。幼いころは自分にはない傷あとが姉と弟の首に残るのを見て「何があったんだろう」と思うだけだった。
戦後の島には首に包帯を巻いた人や、気のふれた人が珍しくなかった。戦時中、国民学校の国語教師として「お国のために」と説いた両親は、戦後、教壇を去った。宮里さんも、戦争の記憶を避けるようにして戦後を生きる。「私は、あの場から逃げた」という思いが頭を離れなかったからだ。「まじめに考えたら生きていけなかった。気のふれた人のほうが、まともだったとさえ思ったのです」》
(中略)
《戦後を「基地の島」として生きることを強いられてきた沖縄県民の思いは、鳩山政権が米軍普天間飛行場(宜野湾市)の県外移設を断念し、名護市辺野古沖を移設先としたことで、「差別」という言葉に収れんしていく。
「沖縄はなぜ今も新しい基地を背負わされようとしているの」。宮里さんも古希を前に初めて、辺野古移設反対の座り込みに参加するようになった。》
宮里さんは、わたしが普天間問題を頻繁に当ブログで書くようになってから、ブログ宛にメールを下さった人の一人である。それからは、お互いのメールアドレスへ、メッセージを往復させる関係になっている。
宮里さんの戦争体験の重さは、すでにある程度は理解しているつもりだったが、このたびの記事中の言葉は、わが胸に、すーっと染み渡った。記事を読んだ当日に、わたしは宮里さんにメールを送っていた。文面の一部はこんな具合だった。
《(前略)ご自分の深い思いと現実のなさけない状況とのギャップに、宮里さんが、いつも胸の張り裂けるような思いでいらっしゃること、わたしにも、一層理解できたように感じられたのです。もちろん新聞記者に伝えたかったことのほんの一部しか紙面には書かれていないとは思います。ですが、やはり、東京新聞の取材に協力されたこと自体の意味は大きいと、あえて申し上げたいと思います。読ませていただけたことに、感謝いたします(後略)》
宮里さんは、東京から送られてきた実際の掲載紙面を読んだ上で、メールの返信を下さった。そこには「取り留めのない話を見事にまとめられ」たと、担当の小嶋記者を評価する言葉があり、わたしは安堵した。蛇足を言えば、マスメディアの中には取材対象者に対して「そういうつもりで話したんじゃない。やっぱり理解してくれなかった」と思わせるような、力不足の取材者たちも意外に多いからである。
それから、小嶋記者が今後も辺野古テント村や沖縄のことを取材したいと考えていると知り、宮里さんも期待を寄せている旨、併せて記されていた。
東京新聞の報道姿勢と一人ひとりの記者の意欲には、わたしもこの場を借りて改めて、期待を込めつつ敬意を表したい。
東京新聞、がんばれ!!
連載の「上」の記事に戻るが、初めに読谷村チビチリガマでの集団自決、次に座間味村での集団自決の事実を、その生き地獄を生き延びた人の証言を通して記し、最後に作家・大城立裕氏の次のような言葉を紹介しつつ、結んでいる。
《「沖縄には、明治維新による『琉球処分』の歴史があります。沖縄差別の原点です。沖縄戦での住民被害に、政府や軍は責任をみようとしなかった。それも差別の繰り返し。そして今、政府は辺野古に強引に恒久基地を造ろうしている。第二の『琉球処分』だといわれるのも、無理はありません」
◇
沖縄戦には「差別」の歴史が凝縮されている。それは米軍との悲壮な地上戦に、住民が駆り出される導火線となった。〝普天間移設〟をめぐり今、沖縄では再び「差別」の声が上がる。怒りの源流を沖縄戦にたどった。》
連載の「中」(6月16日)では、反戦・平和運動に熱心な彫刻家として知られる金城実氏を描き、「下」(17日)では、「鉄血勤皇隊」の一員として学徒動員させられ、戦後は、米軍統治下の立法院議員、県議会議員を経て衆議院議員をつとめた古堅実吉氏をクローズアップしていた。
なぜ、沖縄には「反戦・平和」の強い意志を貫く人が多いのかが、よく伝わる内容だった。沖縄戦をはじめ、沖縄の歴史を学ぶことが、日本国民にとってどれほど大切なことか。行間に、そう訴える声が立ち上ってくる記事である。
沖縄では、梅雨が明けたようである。
その日に、全国高校野球選手権・沖縄大会開幕。グッドタイミングである。
そういう日に、B社の老舗スポーツ雑誌「N」の編集者Uさんと電話で話すこととなったが、要するに、沖縄大会の取材・執筆の依頼であった。編集部のお目当てのチームとわたしのそれとが合致したので、ありがとうねー、がんばりまっせ、である。ちょいとこの夏の予定を練り直さないといけないな。
今後も一所懸命、わたしなりのやり方で普天間問題を考え続ける所存だが、一方では楽しい夏になりそうである。
さて今宵は、「日本vsオランダ」だ。あ、もちろんワールドカップ・サッカーの話。
しかしわたしは、夜中の再放送で観ることに決めた。
21時からは、「NHKスペシャル」に注目。そっちを優先することにした。
本日の東京新聞・テレビ欄の解説を読んで、無視できなくなってしまった。こう書いてあったのだ。
《本土と沖縄の断絶に引き裂かれ、破滅していった若泉敬さんの生涯を通して、今、日米間の最大の懸案となっている〝沖縄問題〟の深層を描き出す。1972年に「核抜き・本土並み」をうたって実現した沖縄返還。しかし、その裏では、「有事の核の再持ち込み」を認める密約が、日米首脳の間で取り交わされていた》
密約の存在自体は、ようやく多くの人の知るところになったわけだが、密約のシナリオを書き、最近になって自死を遂げた若泉氏について、わたしは本当のところをほとんど知らない。気になって仕方がない。
きょうはじつにいろんなことが重なっている。
ある大切な人の誕生日なのでもあるが、メッセージを送っただけで、なんにもできず、歯がゆい(思わせぶりな書き方だが、少し理由あり、なのである)。いい歳をして、昨今おのれの現状を嘆き続けている気もするが、いや、歳は関係ない。このトホホな現実をこそ、今はきちんと噛みしめないといけないのだ。
誰に頼まれたわけでもない断酒生活も、昨日でまる10ヵ月を経過した。思うようにいかないことだらけの毎日だけれど、ごく当たり前に「きょうという日を感謝して生きる」しかないよね。
東京は湿度の高い猛暑である。ふーっ、がんばるぞよーっ。
とくに「こちら特報部」は、基地問題、普天間問題にも切り込むことが多いので、注目している。しかしこの「特報」面はWEBでは読めない。沖縄に帰るときには、月額わずか105円払えば携帯電話で「特報」面などが読めるという、その契約を必ずしようと思っている。「辺野古浜通信」ブログの管理人さんは、東京新聞の愛読者なので、次のような紹介を時々してくれている。→http://henoko.ti-da.net/e2926927.html
その東京新聞が、6月14日、16日、17日の3回にわたり、社会面において「沖縄」特集記事を連載した。
通しタイトルは、
記憶 戦後65年
新聞記者が受け継ぐ戦争 沖縄戦「差別」の源流
というもので、上・中・下の3回にわけての記事であった。
社会部・佐藤直子・小嶋麻友美、と署名があるから、二人の記者の共同作業らしい。
「上」では、
基地の島 また「捨て石」
「第2の琉球処分」に怒り
との大見出しが掲げられている。
わたしは、記事を少し読み進んだところで、あっ、と小さな声をあげた。
沖縄戦時の座間味島での集団自決についての記述の中に、ブログ仲間でメル友で人生の先輩であるところの、「知人」の名前を発見したからだ。その部分を引用する。
《本島より一週間ほど早く、米軍の空襲を受けた慶良間諸島・座間味島でも、百三十人余の村人が避難していた壕で、手りゅう弾を使ったり肉親同士で手をかけたりして絶命した。当時四歳の宮里洋子さん(69)は「死ぬのいやー」と叫んで、かみそりを握った母から逃げた。だが、その記憶は宮里さんにはない。幼いころは自分にはない傷あとが姉と弟の首に残るのを見て「何があったんだろう」と思うだけだった。
戦後の島には首に包帯を巻いた人や、気のふれた人が珍しくなかった。戦時中、国民学校の国語教師として「お国のために」と説いた両親は、戦後、教壇を去った。宮里さんも、戦争の記憶を避けるようにして戦後を生きる。「私は、あの場から逃げた」という思いが頭を離れなかったからだ。「まじめに考えたら生きていけなかった。気のふれた人のほうが、まともだったとさえ思ったのです」》
(中略)
《戦後を「基地の島」として生きることを強いられてきた沖縄県民の思いは、鳩山政権が米軍普天間飛行場(宜野湾市)の県外移設を断念し、名護市辺野古沖を移設先としたことで、「差別」という言葉に収れんしていく。
「沖縄はなぜ今も新しい基地を背負わされようとしているの」。宮里さんも古希を前に初めて、辺野古移設反対の座り込みに参加するようになった。》
宮里さんは、わたしが普天間問題を頻繁に当ブログで書くようになってから、ブログ宛にメールを下さった人の一人である。それからは、お互いのメールアドレスへ、メッセージを往復させる関係になっている。
宮里さんの戦争体験の重さは、すでにある程度は理解しているつもりだったが、このたびの記事中の言葉は、わが胸に、すーっと染み渡った。記事を読んだ当日に、わたしは宮里さんにメールを送っていた。文面の一部はこんな具合だった。
《(前略)ご自分の深い思いと現実のなさけない状況とのギャップに、宮里さんが、いつも胸の張り裂けるような思いでいらっしゃること、わたしにも、一層理解できたように感じられたのです。もちろん新聞記者に伝えたかったことのほんの一部しか紙面には書かれていないとは思います。ですが、やはり、東京新聞の取材に協力されたこと自体の意味は大きいと、あえて申し上げたいと思います。読ませていただけたことに、感謝いたします(後略)》
宮里さんは、東京から送られてきた実際の掲載紙面を読んだ上で、メールの返信を下さった。そこには「取り留めのない話を見事にまとめられ」たと、担当の小嶋記者を評価する言葉があり、わたしは安堵した。蛇足を言えば、マスメディアの中には取材対象者に対して「そういうつもりで話したんじゃない。やっぱり理解してくれなかった」と思わせるような、力不足の取材者たちも意外に多いからである。
それから、小嶋記者が今後も辺野古テント村や沖縄のことを取材したいと考えていると知り、宮里さんも期待を寄せている旨、併せて記されていた。
東京新聞の報道姿勢と一人ひとりの記者の意欲には、わたしもこの場を借りて改めて、期待を込めつつ敬意を表したい。
東京新聞、がんばれ!!
連載の「上」の記事に戻るが、初めに読谷村チビチリガマでの集団自決、次に座間味村での集団自決の事実を、その生き地獄を生き延びた人の証言を通して記し、最後に作家・大城立裕氏の次のような言葉を紹介しつつ、結んでいる。
《「沖縄には、明治維新による『琉球処分』の歴史があります。沖縄差別の原点です。沖縄戦での住民被害に、政府や軍は責任をみようとしなかった。それも差別の繰り返し。そして今、政府は辺野古に強引に恒久基地を造ろうしている。第二の『琉球処分』だといわれるのも、無理はありません」
◇
沖縄戦には「差別」の歴史が凝縮されている。それは米軍との悲壮な地上戦に、住民が駆り出される導火線となった。〝普天間移設〟をめぐり今、沖縄では再び「差別」の声が上がる。怒りの源流を沖縄戦にたどった。》
連載の「中」(6月16日)では、反戦・平和運動に熱心な彫刻家として知られる金城実氏を描き、「下」(17日)では、「鉄血勤皇隊」の一員として学徒動員させられ、戦後は、米軍統治下の立法院議員、県議会議員を経て衆議院議員をつとめた古堅実吉氏をクローズアップしていた。
なぜ、沖縄には「反戦・平和」の強い意志を貫く人が多いのかが、よく伝わる内容だった。沖縄戦をはじめ、沖縄の歴史を学ぶことが、日本国民にとってどれほど大切なことか。行間に、そう訴える声が立ち上ってくる記事である。
沖縄では、梅雨が明けたようである。
その日に、全国高校野球選手権・沖縄大会開幕。グッドタイミングである。
そういう日に、B社の老舗スポーツ雑誌「N」の編集者Uさんと電話で話すこととなったが、要するに、沖縄大会の取材・執筆の依頼であった。編集部のお目当てのチームとわたしのそれとが合致したので、ありがとうねー、がんばりまっせ、である。ちょいとこの夏の予定を練り直さないといけないな。
今後も一所懸命、わたしなりのやり方で普天間問題を考え続ける所存だが、一方では楽しい夏になりそうである。
さて今宵は、「日本vsオランダ」だ。あ、もちろんワールドカップ・サッカーの話。
しかしわたしは、夜中の再放送で観ることに決めた。
21時からは、「NHKスペシャル」に注目。そっちを優先することにした。
本日の東京新聞・テレビ欄の解説を読んで、無視できなくなってしまった。こう書いてあったのだ。
《本土と沖縄の断絶に引き裂かれ、破滅していった若泉敬さんの生涯を通して、今、日米間の最大の懸案となっている〝沖縄問題〟の深層を描き出す。1972年に「核抜き・本土並み」をうたって実現した沖縄返還。しかし、その裏では、「有事の核の再持ち込み」を認める密約が、日米首脳の間で取り交わされていた》
密約の存在自体は、ようやく多くの人の知るところになったわけだが、密約のシナリオを書き、最近になって自死を遂げた若泉氏について、わたしは本当のところをほとんど知らない。気になって仕方がない。
きょうはじつにいろんなことが重なっている。
ある大切な人の誕生日なのでもあるが、メッセージを送っただけで、なんにもできず、歯がゆい(思わせぶりな書き方だが、少し理由あり、なのである)。いい歳をして、昨今おのれの現状を嘆き続けている気もするが、いや、歳は関係ない。このトホホな現実をこそ、今はきちんと噛みしめないといけないのだ。
誰に頼まれたわけでもない断酒生活も、昨日でまる10ヵ月を経過した。思うようにいかないことだらけの毎日だけれど、ごく当たり前に「きょうという日を感謝して生きる」しかないよね。
東京は湿度の高い猛暑である。ふーっ、がんばるぞよーっ。
Posted by watanatsu at 19:11
│時事問題