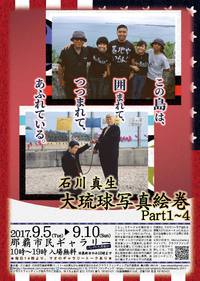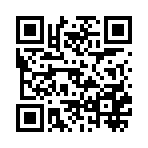2010年11月30日
読売新聞の「犯罪的社説」再び。沖縄県知事選挙を振り返って・1
予定より寝坊をして更新が遅れました。こんにちは。
本題に入る前に、知事選・雑感。
わたしはこのたびの沖縄県知事選挙において、初体験をした。
投開票日を前にして、連日ブログを通じ、特定の候補への支持を表明したのである。
「支持政党なし、無党派層」のカテゴリーに分類される人間が、しかも、日ごろ選挙運動などに関わりを持ちたくないと思うタイプの人間が、ここまでするのは、まったくもって珍しいことなのであった。
理由は、単純だ。沖縄の歴史の上に「大転換点」として刻まれることになるやも知れぬビッグ・イベントに、無関心を装いたくはなかった。悔いを残したくなかったからである。
立場を鮮明にしつつ、「普天間問題」に思いを致した結果、想像以上にいろんなことが見えてきた。それが、これからさまざまな場で書いていく文章に、きっと良い影響を与えるだろうと思えている。
昨日、一連の自分のブログを、冷静に読み返してみたが、間違ったことは書いていなかった(気づいた誤字などは、さりげなく修正しました。あしからずご了承を)ので、われながら安堵した。
選挙の結果が出たことで、これから何を書いていくべきか、かなり具体的に見えてきている。
もちろん昨日は、ネットで全国紙の社説をチェックした(朝日、読売、毎日、日経、産経の5紙)。こういう節目には、沖縄と本土メディアの「温度差」をきちんと把握しておく必要があるからである。
これまでにも当ブログで繰り返し指摘してきたが、読売新聞は、やっぱりとことん「対米追従・沖縄切り捨て」の犯罪的論説を垂れ流して恥じない新聞だ。おバカ丸出し論説委員がデカい顔をしていて、さぞ良心ある記者たちは苦労していることだろうと察せられる。日経、産経も、やはり相変わらず、同罪で論外。「犯罪的論説」を打ち出している。
それらの論説をひと言で要約すれば、実現不可能な「普天間基地の辺野古周辺への移設」を前提とした日米合意を最善策であるかのように錯覚したまま、おぞましいまでの「確信犯的思考停止」に陥ったまま、である(「週刊金曜日」11月12日号なども含めて、わたしはすでに同様のことを書いてきた)。
おバカな社説を三つとも解説するのはエネルギーの無駄なので、代表選手(日本一の部数を発行している新聞、という恐ろしい意味合いもあるので)の読売社説を全文引用紹介した上で、批判を加えておこう。
201011月29日付、読売新聞社説【沖縄知事再選 普天間移設の前進を追求せよ】
↓↓↓
沖縄県が引き続き政府と連携し、米軍普天間飛行場の県内移設にも含みを残す――。それが県民の選択だった。
沖縄県知事選で、現職の仲井真弘多知事が再選された。米軍普天間飛行場の国外移設を主張していた新人の伊波洋一・前宜野湾市長は及ばなかった。
これで、普天間飛行場を名護市辺野古に移設するとした5月の日米合意の早期進展が期待できるわけではない。知事は県外移設を求めているうえ、名護市長も受け入れに反対しているからだ。
知事は、基地負担の大幅軽減を求めて伊波氏に投票した多数の県民への配慮も求められよう。
仮に伊波氏が当選していれば、事態は深刻だった。非現実的な国外移設に固執し、普天間飛行場は現在の危険な状態のまま長期間固定化する恐れがあった。
仲井真知事は昨年まで辺野古移設を支持し、今も県内移設への反対は明言していない。政府との協議に応じる意向も示している。
菅政権は、仲井真知事との対話を重ね、日米合意へ理解を得るよう最大限の努力をすべきだ。
そのためには、普天間飛行場の移設や在沖縄海兵隊8000人のグアム移転後の米軍施設の跡地利用や地域振興で、具体的な将来展望を示すことが重要だ。沖縄の過重な基地負担の一層の軽減を追求することも必要となろう。
尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件や北朝鮮による韓国・延坪島(ヨンピョンド)砲撃で、在日米軍の抑止力の重要性は増している。
今月13日の日米首脳会談では、来年春の菅首相の訪米と日米同盟深化に関する共同文書の発表で合意した。この文書を意味のあるものにするには、普天間問題の一定の前進が不可欠だ。
ところが、菅政権は、あまりに普天間問題に無為無策だった。
自民党政権は、過去の沖縄県知事選や名護市長選で、普天間移設に理解を示す候補を全力で支援してきた。民主党は今回、沖縄選出の党所属国会議員らが伊波氏を応援するのを黙認した。
菅首相が、本当に日米合意を実現し、同盟を深化させる気があるのか、疑わしい。
普天間問題は、14年間に及ぶ曲折を経てきた。昨年、ようやく現実味を帯びてきた辺野古移設をいったん白紙に戻し、米国、沖縄双方との関係を悪化させたのは民主党政権である。
どんなに困難でも、菅政権は、日米合意を前に進めるという重い責任を負っている。(2010年11月29日01時47分 更新のYOMIURI ONLINEの記事より)
一見、沖縄の民意に理解を示す態度を装っているが、騙されてはいけない。
読売社説の本音は、これまでずっと、一貫している。最後の一行にそれが集約されている。
沖縄の民意がどうであっても、日本政府はつべこべ言わずに、日米合意を踏襲して辺野古新基地建設を強行せよ、と言っているだけなのである。
しかも、その根拠たるや、勉強不足も甚だしい低レベル。
怒りを通り越して、あきれ、嗤(わら)いたくなる。
まず第一に、在沖海兵隊は「抑止力」などには成り得ない、という点を、読売、産経、日経などは無視している。意図的であれば、「確信犯的」に世論を間違った方向へ誘導しようとする論説であるし、「海兵隊は抑止力にあらず」という、こんな明白な事実を本当に知らない論説委員であれば、これはもう本当に不勉強極まりない低レベルを露呈していることになる。
先日、述べたように、「在沖縄海兵隊不要論」を、アメリカの共和党・民主党双方の有力議員が唱えているという事実がある。あるいは、日米の信頼できる軍事・安全保障専門家が、「海兵隊をアメリカ本国にすべて戻すべきだ」という意見さえ噴出させている。そういう時代に、日本の大手メディアは、その事実さえ国民に知らせようとしない。
なぜそういうことが起こるのか。メディアの陥っている構造的問題が、間違いなくありそうだ。
各新聞のワシントン特派員というのは、いわばエリート中のエリートたちである。
彼らは、外務省の、同じくエリートである在米大使館員たちと現地で仲良くなる。
この二つのグループは、当然というべきか、ホワイトハウスやペンタゴン(国防総省)にベッタリである。
アメリカさんの意向をいち早く理解し、その狙いどおりに日本を動かそうとする者が、外務省でもメディアの中でも出世する仕組みが出来上がってしまっている。
こうして対米追従、いや対米隷属の「官僚&メディア」のタッグチームが出来上がっている。
彼らの思い通りに、およそ世論誘導は「成功」している。
その典型が、アメリカの望みどおりに辺野古の海に新基地を建設しなければ、日米同盟は危うくなる、という論説の垂れ流しの繰り返し。
それを、怒りを通り越して嗤えるほどのおバカさんたちの主張だ、と指摘する当ブログのような存在は、圧倒的に少数派である。
だがしかし、いや、だからこそ、わたしは「普天間問題」に関する情報発信をやめるわけにはいかないのである。
だからこそ、琉球新報の与那嶺路代ワシントン特派員や平安名純代ロサンゼルス通信員には、これからも、もっともっと頑張ってもらいたいのである。
わたしはよくこういう表現をする。
百歩譲って、日米同盟とは、それはそれは大切なものだと認めたとする。
しかし、その大切な日米同盟を堅持するために、在沖縄海兵隊は、なんの関係もない存在なのである。
海兵隊が抑止力だというのはユクシ(=嘘)。それがむしろ沖縄では常識になりつつある。
なのに、大新聞の論説委員たちは、その事実に知らんぷりを決め込んでいるわけだ。
またしかし、次々と公開されてきた外交文書からも読み取れる。
アメリカ自身が重要視していない基地を、むしろ日本政府が懇願して、沖縄に置き続けることを決めてきただけだという経緯が!!(この点は、いずれ改めて解説したい)。
そのことに、沖縄県民は、改めて怒りを膨らませている。
もうひとつ大切な観点がある。
この国の安全保障を考えるとき、「あなたの立脚点はどこですか?」という話である。
沖縄を踏みつけて平然としている官僚や政治家やメディア業界の従事者たちには、即刻普天間基地の危険や騒音を除去してほしいと願っている人の思いに対しても、そして、万一新基地建設が強行されることになったとき、名護市東海岸地域に住む人びと(地元住民は辺野古区だけにいるのではない)が、どれほどの苦しみを味わうことになるのかについても、まるで想像力が働いていない。あるいは、意図的に想像力を排除している人びとである。
わたしの知る限り、普天間基地周辺に住み、基地被害の除去を真剣に訴えている宜野湾市民のなかで、自分の痛みを辺野古周辺の人びとに押し付けてよしとする人、すなわち「県内移設やむなし」などという考えの持ち主は、皆無に等しい。
沖縄には「ちむぐりさん」という言葉がある。直訳すると、「肝(こころ)が苦しい」。
ヤマトの人間が誰かを指して「かわいそうだ」というような場面で、ウチナーンチュの一定年齢以上の人の胸に芽生える心性である(ウチナーグチに親しまなくなった若い世代に理解できるかどうか、少し疑問は残る)。
相手の苦しんでいる姿を見て、そのまま自分の心が苦しいと感じることができる。
これがウチナーンチュが受け継いできたDNAのなかにある、大切な心の動きなのである。
わたしは「普天間問題」を考えるとき、いつでも「名護市東海岸」に立つことを選ぶ。それが、多くの心あるウチナーンチュたちに、限りなく近い立場であると信じている。
対して、徹底した「沖縄差別」主義者であることを少しも恥じない官僚や政治家と並ぶ、主犯格「実行犯」。それが日本一売れている新聞、読売新聞の社説である(くどいようだが、日経の「社説」、産経の「主張」も同罪である)。
こういう輩と対峙するには、やはり沖縄内部で「保守対革新」などという争いをしている場合ではない。それこそ「県民の心をひとつに」して、「新しい沖縄へ」、一歩踏み出さねばならないはずである。
(このシリーズは、まだ続きます。次回取り上げるのは、昨夜放送されたNHK「クローズアップ現代」内での担当記者による「犯罪的解説」について、です)

本題に入る前に、知事選・雑感。
わたしはこのたびの沖縄県知事選挙において、初体験をした。
投開票日を前にして、連日ブログを通じ、特定の候補への支持を表明したのである。
「支持政党なし、無党派層」のカテゴリーに分類される人間が、しかも、日ごろ選挙運動などに関わりを持ちたくないと思うタイプの人間が、ここまでするのは、まったくもって珍しいことなのであった。
理由は、単純だ。沖縄の歴史の上に「大転換点」として刻まれることになるやも知れぬビッグ・イベントに、無関心を装いたくはなかった。悔いを残したくなかったからである。
立場を鮮明にしつつ、「普天間問題」に思いを致した結果、想像以上にいろんなことが見えてきた。それが、これからさまざまな場で書いていく文章に、きっと良い影響を与えるだろうと思えている。
昨日、一連の自分のブログを、冷静に読み返してみたが、間違ったことは書いていなかった(気づいた誤字などは、さりげなく修正しました。あしからずご了承を)ので、われながら安堵した。
選挙の結果が出たことで、これから何を書いていくべきか、かなり具体的に見えてきている。
もちろん昨日は、ネットで全国紙の社説をチェックした(朝日、読売、毎日、日経、産経の5紙)。こういう節目には、沖縄と本土メディアの「温度差」をきちんと把握しておく必要があるからである。
これまでにも当ブログで繰り返し指摘してきたが、読売新聞は、やっぱりとことん「対米追従・沖縄切り捨て」の犯罪的論説を垂れ流して恥じない新聞だ。おバカ丸出し論説委員がデカい顔をしていて、さぞ良心ある記者たちは苦労していることだろうと察せられる。日経、産経も、やはり相変わらず、同罪で論外。「犯罪的論説」を打ち出している。
それらの論説をひと言で要約すれば、実現不可能な「普天間基地の辺野古周辺への移設」を前提とした日米合意を最善策であるかのように錯覚したまま、おぞましいまでの「確信犯的思考停止」に陥ったまま、である(「週刊金曜日」11月12日号なども含めて、わたしはすでに同様のことを書いてきた)。
おバカな社説を三つとも解説するのはエネルギーの無駄なので、代表選手(日本一の部数を発行している新聞、という恐ろしい意味合いもあるので)の読売社説を全文引用紹介した上で、批判を加えておこう。
201011月29日付、読売新聞社説【沖縄知事再選 普天間移設の前進を追求せよ】
↓↓↓
沖縄県が引き続き政府と連携し、米軍普天間飛行場の県内移設にも含みを残す――。それが県民の選択だった。
沖縄県知事選で、現職の仲井真弘多知事が再選された。米軍普天間飛行場の国外移設を主張していた新人の伊波洋一・前宜野湾市長は及ばなかった。
これで、普天間飛行場を名護市辺野古に移設するとした5月の日米合意の早期進展が期待できるわけではない。知事は県外移設を求めているうえ、名護市長も受け入れに反対しているからだ。
知事は、基地負担の大幅軽減を求めて伊波氏に投票した多数の県民への配慮も求められよう。
仮に伊波氏が当選していれば、事態は深刻だった。非現実的な国外移設に固執し、普天間飛行場は現在の危険な状態のまま長期間固定化する恐れがあった。
仲井真知事は昨年まで辺野古移設を支持し、今も県内移設への反対は明言していない。政府との協議に応じる意向も示している。
菅政権は、仲井真知事との対話を重ね、日米合意へ理解を得るよう最大限の努力をすべきだ。
そのためには、普天間飛行場の移設や在沖縄海兵隊8000人のグアム移転後の米軍施設の跡地利用や地域振興で、具体的な将来展望を示すことが重要だ。沖縄の過重な基地負担の一層の軽減を追求することも必要となろう。
尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件や北朝鮮による韓国・延坪島(ヨンピョンド)砲撃で、在日米軍の抑止力の重要性は増している。
今月13日の日米首脳会談では、来年春の菅首相の訪米と日米同盟深化に関する共同文書の発表で合意した。この文書を意味のあるものにするには、普天間問題の一定の前進が不可欠だ。
ところが、菅政権は、あまりに普天間問題に無為無策だった。
自民党政権は、過去の沖縄県知事選や名護市長選で、普天間移設に理解を示す候補を全力で支援してきた。民主党は今回、沖縄選出の党所属国会議員らが伊波氏を応援するのを黙認した。
菅首相が、本当に日米合意を実現し、同盟を深化させる気があるのか、疑わしい。
普天間問題は、14年間に及ぶ曲折を経てきた。昨年、ようやく現実味を帯びてきた辺野古移設をいったん白紙に戻し、米国、沖縄双方との関係を悪化させたのは民主党政権である。
どんなに困難でも、菅政権は、日米合意を前に進めるという重い責任を負っている。(2010年11月29日01時47分 更新のYOMIURI ONLINEの記事より)
一見、沖縄の民意に理解を示す態度を装っているが、騙されてはいけない。
読売社説の本音は、これまでずっと、一貫している。最後の一行にそれが集約されている。
沖縄の民意がどうであっても、日本政府はつべこべ言わずに、日米合意を踏襲して辺野古新基地建設を強行せよ、と言っているだけなのである。
しかも、その根拠たるや、勉強不足も甚だしい低レベル。
怒りを通り越して、あきれ、嗤(わら)いたくなる。
まず第一に、在沖海兵隊は「抑止力」などには成り得ない、という点を、読売、産経、日経などは無視している。意図的であれば、「確信犯的」に世論を間違った方向へ誘導しようとする論説であるし、「海兵隊は抑止力にあらず」という、こんな明白な事実を本当に知らない論説委員であれば、これはもう本当に不勉強極まりない低レベルを露呈していることになる。
先日、述べたように、「在沖縄海兵隊不要論」を、アメリカの共和党・民主党双方の有力議員が唱えているという事実がある。あるいは、日米の信頼できる軍事・安全保障専門家が、「海兵隊をアメリカ本国にすべて戻すべきだ」という意見さえ噴出させている。そういう時代に、日本の大手メディアは、その事実さえ国民に知らせようとしない。
なぜそういうことが起こるのか。メディアの陥っている構造的問題が、間違いなくありそうだ。
各新聞のワシントン特派員というのは、いわばエリート中のエリートたちである。
彼らは、外務省の、同じくエリートである在米大使館員たちと現地で仲良くなる。
この二つのグループは、当然というべきか、ホワイトハウスやペンタゴン(国防総省)にベッタリである。
アメリカさんの意向をいち早く理解し、その狙いどおりに日本を動かそうとする者が、外務省でもメディアの中でも出世する仕組みが出来上がってしまっている。
こうして対米追従、いや対米隷属の「官僚&メディア」のタッグチームが出来上がっている。
彼らの思い通りに、およそ世論誘導は「成功」している。
その典型が、アメリカの望みどおりに辺野古の海に新基地を建設しなければ、日米同盟は危うくなる、という論説の垂れ流しの繰り返し。
それを、怒りを通り越して嗤えるほどのおバカさんたちの主張だ、と指摘する当ブログのような存在は、圧倒的に少数派である。
だがしかし、いや、だからこそ、わたしは「普天間問題」に関する情報発信をやめるわけにはいかないのである。
だからこそ、琉球新報の与那嶺路代ワシントン特派員や平安名純代ロサンゼルス通信員には、これからも、もっともっと頑張ってもらいたいのである。
わたしはよくこういう表現をする。
百歩譲って、日米同盟とは、それはそれは大切なものだと認めたとする。
しかし、その大切な日米同盟を堅持するために、在沖縄海兵隊は、なんの関係もない存在なのである。
海兵隊が抑止力だというのはユクシ(=嘘)。それがむしろ沖縄では常識になりつつある。
なのに、大新聞の論説委員たちは、その事実に知らんぷりを決め込んでいるわけだ。
またしかし、次々と公開されてきた外交文書からも読み取れる。
アメリカ自身が重要視していない基地を、むしろ日本政府が懇願して、沖縄に置き続けることを決めてきただけだという経緯が!!(この点は、いずれ改めて解説したい)。
そのことに、沖縄県民は、改めて怒りを膨らませている。
もうひとつ大切な観点がある。
この国の安全保障を考えるとき、「あなたの立脚点はどこですか?」という話である。
沖縄を踏みつけて平然としている官僚や政治家やメディア業界の従事者たちには、即刻普天間基地の危険や騒音を除去してほしいと願っている人の思いに対しても、そして、万一新基地建設が強行されることになったとき、名護市東海岸地域に住む人びと(地元住民は辺野古区だけにいるのではない)が、どれほどの苦しみを味わうことになるのかについても、まるで想像力が働いていない。あるいは、意図的に想像力を排除している人びとである。
わたしの知る限り、普天間基地周辺に住み、基地被害の除去を真剣に訴えている宜野湾市民のなかで、自分の痛みを辺野古周辺の人びとに押し付けてよしとする人、すなわち「県内移設やむなし」などという考えの持ち主は、皆無に等しい。
沖縄には「ちむぐりさん」という言葉がある。直訳すると、「肝(こころ)が苦しい」。
ヤマトの人間が誰かを指して「かわいそうだ」というような場面で、ウチナーンチュの一定年齢以上の人の胸に芽生える心性である(ウチナーグチに親しまなくなった若い世代に理解できるかどうか、少し疑問は残る)。
相手の苦しんでいる姿を見て、そのまま自分の心が苦しいと感じることができる。
これがウチナーンチュが受け継いできたDNAのなかにある、大切な心の動きなのである。
わたしは「普天間問題」を考えるとき、いつでも「名護市東海岸」に立つことを選ぶ。それが、多くの心あるウチナーンチュたちに、限りなく近い立場であると信じている。
対して、徹底した「沖縄差別」主義者であることを少しも恥じない官僚や政治家と並ぶ、主犯格「実行犯」。それが日本一売れている新聞、読売新聞の社説である(くどいようだが、日経の「社説」、産経の「主張」も同罪である)。
こういう輩と対峙するには、やはり沖縄内部で「保守対革新」などという争いをしている場合ではない。それこそ「県民の心をひとつに」して、「新しい沖縄へ」、一歩踏み出さねばならないはずである。
(このシリーズは、まだ続きます。次回取り上げるのは、昨夜放送されたNHK「クローズアップ現代」内での担当記者による「犯罪的解説」について、です)
Posted by watanatsu at 11:12
│時事問題