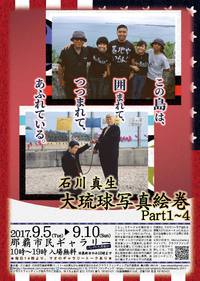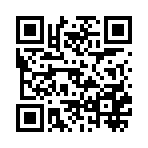2011年07月05日
今、共有してほしい「普天間問題」への認識。6月27日の備忘録・3
高校野球の取材で、八重山商工の敗北と八重山高校の充実ぶりを見届け、それから琉球キングスの桶谷大ヘッドコーチとFC琉球の新里裕之監督を囲む会で有意義な時間を過ごした一日。
じつは、その日の琉球新報・文化面に、重要な論考が掲載されていた。
沖縄国際大学教授(政治学)の佐藤学さんが担当する「時評2011」の6月分の記事であった。
全国メディアに接しているだけでは、おそらくちんぷんかんぷんであろう、6月21日の「2プラス2」における日米合意の欺瞞についての、非常にわかりやすい解説だ。
強引に簡略化して感想を述べれば、「わたしたちは日米合意の茶番に惑わされなくてよいのだな。辺野古新基地建設などまるで不可能なのだ。これからも、普天間基地の県外・国外移設要求を、粘り強く続けていこう」と思える論考だった。
「普天間問題の今」を語るとき、すべての人の議論の土台に据えてほしい、とさえいえる良識的解説であったのだ。
この論考は、すでに「地元紙で識るオキナワ」ブログhttp://michisan.ti-da.net/e3610992.htmlでも紹介されているが、少し読みにくかったので、わたしは紙面からすべて書き写してみた。個人的な資料保存の意味でいえば、新聞をコピーした紙をファイルしておけば済む話だが、やはり多くの人に読んでほしいと思ったので、ここに全文引用紹介する次第。
米国議会と政府の意思決定の動向には、今後も注目が必要だが、6月下旬の時点での、状況把握のおさらいをするためにも、ぜひじっくり読んでいただきたい。
*
琉球新報・2011年6月27日・文化面(15面)
「時評2011」[6月]
佐藤学
[実現性ない2プラス2合意]
基地削減、米に動き
日本政府と国民が阻止
6月21日にワシントンで開催された日米安全保障協議委員会(2プラス2)は、米海兵隊普天間航空基地の代替施設として、名護市辺野古の「V字案」新基地建設を「決定」した。これにより「普天間返還問題」は、最終的な決着に至った、ということを受け入れる者は、少なくとも沖縄県内にはほとんどいないであろう。
沖縄県知事が県内移設を受け入れておらず、地元・名護市も辺野古新基地建設反対の立場を堅持している。県内で公的に選ばれた政治的代表のほとんどが辺野古案に反対している中、この「決定」に実現可能性はない。
慰霊の日に来県した菅直人首相は、沖縄の県外移設要求は理解できるが、「いろいろ検討してきた」結果、それは難しいとの発言をしている。民主党政権も、沖縄の主張を受け入れる意図を持たず、「いろいろ検討」など一切していない事実は、沖縄では従前から指摘されてきたが、5月にウスキリークスが公開した米国政府外交公電で、図らずも証明された。
民主党政権の外務・防衛官僚が、米国に対して、沖縄への強硬な姿勢を保つように依頼すらし、閣僚が早い時期から辺野古回帰で動いていた実態が明るみに出ている。2月の鳩山前首相インタビューにも、閣僚、官僚が、県外・国外移設の模索をつぶした証言がある。全国メディアは、これらの報道を浅く流した。しかし、当事者としての沖縄は、日本政府が何をしてきたのかを注視してきた。菅首相は、見え透いた嘘で言い逃れできると考えているのだろうが、それは沖縄県民への愚弄である。
辺野古は「非現実的」
沖縄の側が投げかけてきた正当な主張は、残念なことに、日本政府を動かすことができなかった。しかし、意外にも、米国内の政治状況が、沖縄の要求に沿う解決策を可能にする条件を作り出してきた。米国政府の予算決定権を持つ米国連邦議会が、辺野古案の実現可能性を厳しく問う事態となっている。4月27日に来沖したレビン上院軍事委員長らが、5月11日に、グアムと辺野古への海兵隊移転計画を非現実的と批判する声明を出したが、その後、6月17日に、軍事予算審議過程で、上院軍事委員会はグアム、辺野古関連予算を削除する案を提出した。
5月25日には、連邦議会GAO(会計検査局)が、グアム、辺野古移転計画について、予算面の強い批判を盛り込んだ報告書を出した。米国GAOは、日本の会計検査院とは全く異なる「政策評価」を実施する機関であり、その報告書は、中立的であり、かつ議会の権威を背景として、重く受け止められる。2009年の「グアム移転協定」の中で、米側負担として決められたグアム海兵隊基地建設関連の40億ドルは、GAOの試算では110億ドルに肥大し、一方、辺野古建設に伴う沖縄県内での移転に関しては、米側負担の見積もりが一切ないため、総額がどれだけになるか全く不明であると批判している。
「抑止力は問題ない」
辺野古予算を批判している上院議員には、08年共和党大統領候補者であり、ベトナム戦争の英雄であったマケインや、海兵隊出身で、海軍長官を務め、同じくベトナムの英雄であったウェッブが含まれている。超党派の、しかも軍の側に立つ彼らがなぜ辺野古を批判しているのか。それは、米国国内の財政状況と、それが生み出す国内政治状況が原因である。昨年11月の議会選挙で、劇的な政府財政赤字削減を主張する共和党が下院多数を占め、また、上院でも議席を増やした。08年の金融危機勃発後、米国経済は今も立ち直っておらず、ブッシュ政権が導入した富裕層大減税と、アフガン、イラクの二つの戦争の軍事支出激増により、米国財政は急速に悪化した。
その結果、オバマ政権は、軍事予算を含めた歳出の大幅削減に取り組まざるを得なくなっている。また、この状況は、米国社会の高齢化の進展により、早期に改善される見通しがない。軍事予算が削減される中で、米国は予算の優先順位を厳しく付けていく。アフガン戦争兵力削減の決定も、その線の決定である。対中国の将来を考えた時に、海軍、空軍を優先せざるを得ず、太平洋地域における海兵隊新基地建設は必要性が低いと判断される。
2プラス2での米側の思惑は、日本の負担を大幅に増やさせる点にある。しかし、議会側が指摘しているように、震災後の日本政府に、そのような余力はないことも、自明である。それを受けたレビンたちの主張は、「嘉手納統合」を主要点とするものではない。辺野古は不可能、しかし、普天間は返還する、その条件で手っ取り早いのが嘉手納統合、という論理構成である。これは、空軍機の削減が条件であっても、嘉手納統合は受け入れられないと沖縄が主張し続ければ、県外・国外の別計画に向かう可能性を示す。ウェッブは、嘉手納空軍機の削減が抑止力低下につながらないかとの質問に対し、三沢でもグアムでも、太平洋地域にあるかぎり、抑止力には問題ないと断言している(朝日新聞5月25日朝刊)。ゲーツ国防長官の7月退任が迫り、菅政権の命運が定まらない中で演じられた2プラス2の芝居の陰で、実は在沖米軍基地の本格的削減を可能にする条件が整いつつある。それを阻止しているのは、日本政府であり、日本国民である。
(沖縄国際大学教授)
*
引用終了。
では、本日も希望の光の見える一日となりますように。
じつは、その日の琉球新報・文化面に、重要な論考が掲載されていた。
沖縄国際大学教授(政治学)の佐藤学さんが担当する「時評2011」の6月分の記事であった。
全国メディアに接しているだけでは、おそらくちんぷんかんぷんであろう、6月21日の「2プラス2」における日米合意の欺瞞についての、非常にわかりやすい解説だ。
強引に簡略化して感想を述べれば、「わたしたちは日米合意の茶番に惑わされなくてよいのだな。辺野古新基地建設などまるで不可能なのだ。これからも、普天間基地の県外・国外移設要求を、粘り強く続けていこう」と思える論考だった。
「普天間問題の今」を語るとき、すべての人の議論の土台に据えてほしい、とさえいえる良識的解説であったのだ。
この論考は、すでに「地元紙で識るオキナワ」ブログhttp://michisan.ti-da.net/e3610992.htmlでも紹介されているが、少し読みにくかったので、わたしは紙面からすべて書き写してみた。個人的な資料保存の意味でいえば、新聞をコピーした紙をファイルしておけば済む話だが、やはり多くの人に読んでほしいと思ったので、ここに全文引用紹介する次第。
米国議会と政府の意思決定の動向には、今後も注目が必要だが、6月下旬の時点での、状況把握のおさらいをするためにも、ぜひじっくり読んでいただきたい。
*
琉球新報・2011年6月27日・文化面(15面)
「時評2011」[6月]
佐藤学
[実現性ない2プラス2合意]
基地削減、米に動き
日本政府と国民が阻止
6月21日にワシントンで開催された日米安全保障協議委員会(2プラス2)は、米海兵隊普天間航空基地の代替施設として、名護市辺野古の「V字案」新基地建設を「決定」した。これにより「普天間返還問題」は、最終的な決着に至った、ということを受け入れる者は、少なくとも沖縄県内にはほとんどいないであろう。
沖縄県知事が県内移設を受け入れておらず、地元・名護市も辺野古新基地建設反対の立場を堅持している。県内で公的に選ばれた政治的代表のほとんどが辺野古案に反対している中、この「決定」に実現可能性はない。
慰霊の日に来県した菅直人首相は、沖縄の県外移設要求は理解できるが、「いろいろ検討してきた」結果、それは難しいとの発言をしている。民主党政権も、沖縄の主張を受け入れる意図を持たず、「いろいろ検討」など一切していない事実は、沖縄では従前から指摘されてきたが、5月にウスキリークスが公開した米国政府外交公電で、図らずも証明された。
民主党政権の外務・防衛官僚が、米国に対して、沖縄への強硬な姿勢を保つように依頼すらし、閣僚が早い時期から辺野古回帰で動いていた実態が明るみに出ている。2月の鳩山前首相インタビューにも、閣僚、官僚が、県外・国外移設の模索をつぶした証言がある。全国メディアは、これらの報道を浅く流した。しかし、当事者としての沖縄は、日本政府が何をしてきたのかを注視してきた。菅首相は、見え透いた嘘で言い逃れできると考えているのだろうが、それは沖縄県民への愚弄である。
辺野古は「非現実的」
沖縄の側が投げかけてきた正当な主張は、残念なことに、日本政府を動かすことができなかった。しかし、意外にも、米国内の政治状況が、沖縄の要求に沿う解決策を可能にする条件を作り出してきた。米国政府の予算決定権を持つ米国連邦議会が、辺野古案の実現可能性を厳しく問う事態となっている。4月27日に来沖したレビン上院軍事委員長らが、5月11日に、グアムと辺野古への海兵隊移転計画を非現実的と批判する声明を出したが、その後、6月17日に、軍事予算審議過程で、上院軍事委員会はグアム、辺野古関連予算を削除する案を提出した。
5月25日には、連邦議会GAO(会計検査局)が、グアム、辺野古移転計画について、予算面の強い批判を盛り込んだ報告書を出した。米国GAOは、日本の会計検査院とは全く異なる「政策評価」を実施する機関であり、その報告書は、中立的であり、かつ議会の権威を背景として、重く受け止められる。2009年の「グアム移転協定」の中で、米側負担として決められたグアム海兵隊基地建設関連の40億ドルは、GAOの試算では110億ドルに肥大し、一方、辺野古建設に伴う沖縄県内での移転に関しては、米側負担の見積もりが一切ないため、総額がどれだけになるか全く不明であると批判している。
「抑止力は問題ない」
辺野古予算を批判している上院議員には、08年共和党大統領候補者であり、ベトナム戦争の英雄であったマケインや、海兵隊出身で、海軍長官を務め、同じくベトナムの英雄であったウェッブが含まれている。超党派の、しかも軍の側に立つ彼らがなぜ辺野古を批判しているのか。それは、米国国内の財政状況と、それが生み出す国内政治状況が原因である。昨年11月の議会選挙で、劇的な政府財政赤字削減を主張する共和党が下院多数を占め、また、上院でも議席を増やした。08年の金融危機勃発後、米国経済は今も立ち直っておらず、ブッシュ政権が導入した富裕層大減税と、アフガン、イラクの二つの戦争の軍事支出激増により、米国財政は急速に悪化した。
その結果、オバマ政権は、軍事予算を含めた歳出の大幅削減に取り組まざるを得なくなっている。また、この状況は、米国社会の高齢化の進展により、早期に改善される見通しがない。軍事予算が削減される中で、米国は予算の優先順位を厳しく付けていく。アフガン戦争兵力削減の決定も、その線の決定である。対中国の将来を考えた時に、海軍、空軍を優先せざるを得ず、太平洋地域における海兵隊新基地建設は必要性が低いと判断される。
2プラス2での米側の思惑は、日本の負担を大幅に増やさせる点にある。しかし、議会側が指摘しているように、震災後の日本政府に、そのような余力はないことも、自明である。それを受けたレビンたちの主張は、「嘉手納統合」を主要点とするものではない。辺野古は不可能、しかし、普天間は返還する、その条件で手っ取り早いのが嘉手納統合、という論理構成である。これは、空軍機の削減が条件であっても、嘉手納統合は受け入れられないと沖縄が主張し続ければ、県外・国外の別計画に向かう可能性を示す。ウェッブは、嘉手納空軍機の削減が抑止力低下につながらないかとの質問に対し、三沢でもグアムでも、太平洋地域にあるかぎり、抑止力には問題ないと断言している(朝日新聞5月25日朝刊)。ゲーツ国防長官の7月退任が迫り、菅政権の命運が定まらない中で演じられた2プラス2の芝居の陰で、実は在沖米軍基地の本格的削減を可能にする条件が整いつつある。それを阻止しているのは、日本政府であり、日本国民である。
(沖縄国際大学教授)
*
引用終了。
では、本日も希望の光の見える一日となりますように。
Posted by watanatsu at 13:21
│時事問題