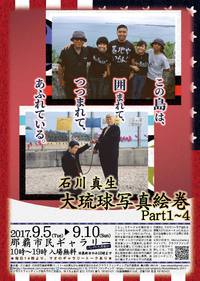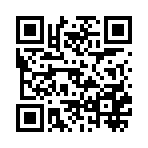2011年12月24日
国境の島・与那国島の現在と未来を想うクリスマス&正月【上】
あえて、タイトルを与那国島に絞り込んだ意味は、読んでくださればわかってもらえるはずなので、しばしお付き合いを。
いわゆる普天間基地の辺野古への移設(とは名ばかりで、明らかに大規模自然破壊を伴う新基地の建設である)を前提とした「辺野古環境アセス評価書」の、政府による県知事への提出は、日米政府による沖縄への「レイプ」に等しい許されざる行為である。その認識が、多くの沖縄県民の間で共有されつつある。それが年内であろうと年明けであろうと「レイプの罪」に変わりはないのである。
何度も書くのがバカらしくなるほどに、沖縄側は繰り返し明確に、「辺野古新基地建設反対」や「普天間基地の県外移設要求」という民意をはっきりと示し続けてきた。県議会の全会一致決議はじめ、沖縄県知事、名護市長、あるいは全41市町村長の意思表明をみれば明らかである。
それでも防衛省の官僚たち、防衛大臣はじめ関係する政治家たち、そして複数の全国メディアは、あたかも沖縄には「民意」が存在しないかのように、振る舞っている。
彼らに対し改めて、強い怒りをこめて、沖縄をなめてはいけないよ、と警告しておこう。
*
さて、目の前にこなすべき個人的課題は山積しているのだが、一方では毎日、与那国島のことを考えている。
18歳と19歳のときに「与那国島サトウキビ刈り援農隊」に参加して以来、何度も通い長期滞在した島である。
島の自然の恵みに抱かれ、島人の情けに助けられた青春の日々。今あらためて振り返ってみても、懐かしくありがたい思いにわが胸は満たされる。
恩義ある島である。
その恩義ある島が、今おかしなことになってしまっている。非常に心配である。
教科書採択問題と自衛隊誘致問題のことである。
石垣市教育委員会(玉津博克教育長)に歩調を合わせるかたちで、与那国町教育委員会(崎原用能教育長)が、問題の「つくる会系」育鵬社の中学公民教科書を選んでしまったのが今年の8月のこと。
教科用図書採択の八重山地区協議会会長を務める玉津博克氏による独善的で拙速な手続き変更を経て、育鵬社版が選ばれてしまったのは周知の通り。
玉津氏が問題の「つくる会系」教科書ありきのお粗末な議事進行をし、協議会の議事録まで改ざんしていたことは、地元紙等の報道で次々に明らかになっている。現場の教師たちの推薦を一切無視する決定をしたことも含めて(つまり、育鵬社版は協議会への推薦さえなかった教科書)、疑惑の多い協議会だったことを、わたしも指摘しておかねばならない。
竹富町教育委員会は、その横暴なやり口に屈せず、育鵬社版を拒否し、竹富町の子供たちのために東京書籍版を選んだ。
しかし、なんと文部科学省は、その竹富町に対して「有償化」を言い、圧力をかけている。
教科書の採択権は、各教育委員会にある、という地方教育行政法からみれば、竹富町の選択にはなんら瑕疵(かし)がないにもかかわらず、である。一方、教科書無償措置法というものもある。無償化のためには、同一採択地区の中で教科書を統一することが前提になっている。
この二つの法律の矛盾が表面に現れた、全国でも初めてのケースだ。
沖縄県の立場ははっきりしている。
八重山地区内の統一をはかるため、9月8日の八重山地区の全13人の教育委員が集まった会合に県の教育委員会はあえて立ち会い、その場で仕切り直した教科書採択を有効とする立場だ。
つまり、育鵬社版を退け、東京書籍版を採択し直した営為を、有効と認めているのだ。
これに対しても、文部科学省は否定する態度を取っている。地区内の統一をはかるよう沖縄県に求めたのは、文部科学省である。そのことを受けて努力した県の英断を否定し、横暴な手続きを進めた協議会の側の決定を支持するのみである。
防衛省の「人でなし」ぶりのみならず、このことを見ても、日本の官僚機構が、いかに劣化し、危険な状態に陥っているかがわかる。共通するのは、確信犯であるか無自覚であるかは別として、官僚・政治家たちの「思考停止」状態である。
わたしは11月初旬に、沖縄大学図書館へ赴いた。マスコミなどを通じて知らされていた一般公開期間は若干過ぎてしまっていたが、一般市民としての当方の閲覧要望に、図書館職員の方たちが丁寧に対応してくださり、問題の育鵬社版と、竹富町教育委員会が選んだ東京書籍版を手に取り、じっくりと読み比べることができた(※地域に開かれた大学を目指しているという沖縄大学のこのような努力に感謝と賛意を表したい)。
二つの教科書の内容は、大きく違っていた。
自衛隊の存在意義をひたすら強調し、沖縄の過重な基地負担など無視しているに等しく、改憲への誘導シュミレーションとすら呼べる記述を展開している育鵬社版(ちなみに表紙の日本列島の写真の中に、奄美や沖縄の島々や小笠原諸島は写っていない。意図的でなくても、編者たちのデリカシーのなさは、こういうところにもくっきり表れている)。
一方、東京書籍版では、「日本の平和主義」という章の中で、目立つ位置に「沖縄と基地」という囲み記事を設けている。決して十分とは言えないまでも、全国の米軍基地面積の74パーセントが沖縄に存在していることにも触れ、沖縄の基地縮小への道について真正面から取り上げられている。環境・人権・平和という、人が生きる上で意識する必要のある「三大要素」に関して、真摯に取り組もうとする姿勢のうかがえる教科書である。
授業で教科書をどう使うのか、一人ひとりの教師の力量が問われることは言うまでもないが、その前段階の採択の話だ。次代を担う中学生たちに、どちらの教科書を使ってほしいか、である。
育鵬社版は、出来が悪いだけではない。沖縄戦における日本軍の関与による集団自決を否定するような、歴史改ざん主義者たち(=新しい歴史教科書をつくる会)の関わっている教科書であることが、まずもって大問題なのである。
その教科書を採択する動きが、あろうことか沖縄県内で起こってしまった。このことに大きなショックと憤りを覚えた沖縄県民は、わたしの周囲だけでも非常に多くいる。
こんな教科書を、ろくな議論もせずに選ぶことをしてしまった八重山採択地区協議会のメンバーと、石垣市教育委員会と与那国町教育委員会の皆さんには、なんと恥ずかしいことをしてしまったのかと気づく日が来てほしいものである。「あの頃は、ある勢力に洗脳されてしまっていたので、何が正しいことか見失っていた」と自覚する日の来ることを願うばかりである。
*
同様の意味で、強引で拙速だと感じさせるのが、与那国島への「自衛隊誘致」「自衛隊配備計画」である。
わたしは町長と町議会による「誘致」の動きを知ったとき、「それは、ちょっと違うんじゃない?」という感想を抱いた。
その理由については、年明けに発売される月刊誌において、与那国の現状に関するルポで書いたので、発売日の前後には、改めてお知らせしたいと思う。
*
そんなふうに、毎日与那国島のことを考えているある日のこと、といってもつい一昨日(12月22日)なのだが、不思議な不思議な体験をすることとなった。
会いたいと思っていた人に、アポなしで会えた。
しかも、わたしがこの沖縄島(沖縄本島)の中で大好きな場所のひとつである海岸で!!
以前から当ブログを読んでくださっている方、あるいは、昨夜フェイスブック上で公開した写真をご覧いただいた方には、言わずもがなかもれしない。
その場所とは、南城市(旧玉城村)の百名(ひゃくな)の浜である。
琉球開闢神話が凝縮して今も息づいている土地。大規模リゾート開発や護岸工事の及んでいない土地。沖縄本島南部では、数少なくなってしまった自然の海岸線の残されている場所。平たく言えば、この一帯は、今も多くの人が「神がかりの場所」と考えているわけだが、そんな百名の浜がわたしも大好きで、ドライブがてら時々訪れる。
じつは5日前の12月19日(22日から数えればわずか3日前)にも、この浜に降りて、深呼吸をし、英気を養ったばかりであった。天気の良い日の夕暮れ時だった。
近所の畑では、サトウキビの花が風に揺れて美しく輝いていた(ススキではないので、念のため…(笑))。
ここまでで、いったんアップします。
(つづく)
Posted by watanatsu at 10:11
│時事問題