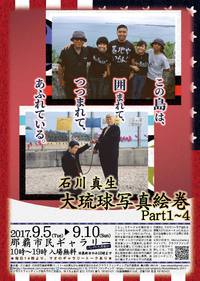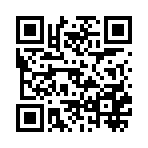2012年02月08日
全国民、注視されたし!! 普天間問題がいよいよ急展開。
じつに10日ぶりのブログ更新になってしまった(もしかしたら、当ブログ史上最長休止記録?)。
このところ、沖縄では、普天間問題を中心とする大問題に連続して急展開があったものだから、これら一連の動きについて、何かまとまったことを書こうと思いつつ(それがいけない!)、更新が遅れてしまった。
まとまりのない断片的な備忘録でも身辺雑記でもよいから、もう少しまめに記事更新していこうと思うこの頃である。
*
沖縄の地元二大紙は、良い意味で互いにライバル心旺盛で、常に切磋琢磨している新聞である。
長引く不況のなかで、両社の合併案も繰り返しささやかれているようだが、わたし個人としては、できればこの健全なライバル関係は続けていただきたいと願っている。
両社の共存が、沖縄の新聞ならではの、日米政府の権力行使に対する正当な批判精神を、今後もより一層発揮することに繋がる。一読者として、大いにそう期待しているのである。
さて、沖縄地元紙が、ますます元気である。
11月28日の防衛省沖縄防衛局の田中聡局長が全国紙記者を含むオフレコ懇談会の席で、辺野古アセス環境評価書の提出時期について問われ、「(犯す前に)犯しますよと言いますか」との暴言を吐き、更迭されたことは、周知の事実であろう。
このオフレコ発言を、翌朝の一面トップでスクープ報道したのは、琉球新報であった。わたしは、当時も今も、この琉球新報の判断は正しいと思っている。「オフ懇」をよいことに政府官僚が沖縄を凌辱する暴言を繰り返し、それが闇に葬られていく。そんなことが見逃されてよいはずがない。看過できない暴言(=政府の本音)は、公共の利益という観点においても、報道されてしかるべきなのだ。
この件に関して沖縄タイムスは、結果的にライバル紙の後塵を拝することになってしまっていたわけだが、ここにきて、米国発のスクープ記事によって気を吐いている。
同紙の平安名純代・米国特約記者が、アメリカでの独自取材をもとに、スクープを発信したのである。
2月4日付・沖縄タイムス1面トップを飾った「米、辺野古断念へ」と大見出しは、非常にインパクトがあった。

ここ数年、米国では、民主・共和両党の軍隊出身の重鎮議員や大学教授、シンクタンクの研究員ら、外交・軍事・安全保障の専門家の間から、普天間移設の名を借りた辺野古新基地建設計画を疑問視する声、米国軍事費の大幅削減の流れを受けて従来の米軍再編計画履行を困難視する声があがり、在沖米海兵隊のアメリカ本土への撤退論など、様々な提言がなされてきた。そしてその声を伝え続けてきたのは、琉球新報や沖縄タイムスである。つまり、通信社や全国メディアのワシントン特派員の配信記事の後追いなどではなく(というか、在米日本大使館ベッタリのワシントン特派員たちほど当てにならない存在はない。いや、彼らこそ日本のジャーナリズムを駄目にしている元凶だと厳しく指摘すべきでさえある)、自前の取材で、真実を明らかにし続けてきたのだ。
これを全国メディアのほとんどが無視し続けてきた実態がある。
これでは、沖縄とヤマト(日本本土)の住民の意識のギャップは広がるばかりである。
それどころか、実現不可能な計画を最善とうそぶく悪名高きケビン・メア元国務省日本部長(沖縄総領事経験者)の著書が売れて、日本の官僚・政治家が大いに影響を受けているらしいなんて話(永田町・霞が関の事情通の話・・・笑)を聞いた日には、まさに開いた口がふさがらない、というしかないわけであった。ケビン・メア君が辺野古新基地建設に固執するのは、彼自身がその計画を強硬に推進した直接の担当者だったからにすぎない。「努力(はっきり言って無駄な努力)」が水泡に帰するのが惜しいだけなのだ。
何はともあれ、沖縄のメディアは、早くから「普天間基地の辺野古移設」なる計画の欺瞞性を見抜き、様々な角度から検証を繰り返してきた。それらの報道に接してきたわたしは、辺野古新基地建設は、実現不可能である、と当ブログでも何度も断言してきた。
そしていよいよ、皮肉なことに、米国の側で「辺野古断念」の動きが加速してきているのである。
全国の皆さんには、今こそ、「辺野古移設が最善」などと繰り返している日本政府のおバカさ加減に気づいてほしい。
そのためには、情報の共有は欠かせない。
真実を伝えようとしない全国メディアはこの際ほうっておいて、沖縄のメディアに常に目を向けていただきたい。
その際に助けになるブログ・ホームページは多々あるけれど、まずはその代表例として、「地元紙で識るオキナワ」というブログを紹介しておこう。ぜひご注目ください。
→http://michisan.ti-da.net/
はじめての方には、遡っていろいろな記事をチェックされることをお勧めしたい。
さて、本日はこれから、八重山教科書問題の行政訴訟の第一回公判の傍聴へ、那覇地裁へ赴きたいと思っている。
本当は、「普天間問題」に関して、もう少しまとまったリポートを書きたいのだが、きょうはこのへんでご勘弁を。
これ以上ブログ更新が滞ることは避けたくて、取り急ぎ記事をアップしました。言葉足らずをご寛容ください。
※それから、改めてのお知らせです。
先にも告知させていただきましたが、『世界』2月号の拙文「与那国島に自衛隊は必要か(上)」の続編、すなわち(下)は、4月号掲載へ変更ですので、何とぞよろしくお願いします。(おそらく3月号は本日東京などで発売されたはずですので)
沖縄は、数日ごとに寒波到来、冷え込んでます。
皆さま体調崩されませぬように。では、また。
このところ、沖縄では、普天間問題を中心とする大問題に連続して急展開があったものだから、これら一連の動きについて、何かまとまったことを書こうと思いつつ(それがいけない!)、更新が遅れてしまった。
まとまりのない断片的な備忘録でも身辺雑記でもよいから、もう少しまめに記事更新していこうと思うこの頃である。
*
沖縄の地元二大紙は、良い意味で互いにライバル心旺盛で、常に切磋琢磨している新聞である。
長引く不況のなかで、両社の合併案も繰り返しささやかれているようだが、わたし個人としては、できればこの健全なライバル関係は続けていただきたいと願っている。
両社の共存が、沖縄の新聞ならではの、日米政府の権力行使に対する正当な批判精神を、今後もより一層発揮することに繋がる。一読者として、大いにそう期待しているのである。
さて、沖縄地元紙が、ますます元気である。
11月28日の防衛省沖縄防衛局の田中聡局長が全国紙記者を含むオフレコ懇談会の席で、辺野古アセス環境評価書の提出時期について問われ、「(犯す前に)犯しますよと言いますか」との暴言を吐き、更迭されたことは、周知の事実であろう。
このオフレコ発言を、翌朝の一面トップでスクープ報道したのは、琉球新報であった。わたしは、当時も今も、この琉球新報の判断は正しいと思っている。「オフ懇」をよいことに政府官僚が沖縄を凌辱する暴言を繰り返し、それが闇に葬られていく。そんなことが見逃されてよいはずがない。看過できない暴言(=政府の本音)は、公共の利益という観点においても、報道されてしかるべきなのだ。
この件に関して沖縄タイムスは、結果的にライバル紙の後塵を拝することになってしまっていたわけだが、ここにきて、米国発のスクープ記事によって気を吐いている。
同紙の平安名純代・米国特約記者が、アメリカでの独自取材をもとに、スクープを発信したのである。
2月4日付・沖縄タイムス1面トップを飾った「米、辺野古断念へ」と大見出しは、非常にインパクトがあった。
ここ数年、米国では、民主・共和両党の軍隊出身の重鎮議員や大学教授、シンクタンクの研究員ら、外交・軍事・安全保障の専門家の間から、普天間移設の名を借りた辺野古新基地建設計画を疑問視する声、米国軍事費の大幅削減の流れを受けて従来の米軍再編計画履行を困難視する声があがり、在沖米海兵隊のアメリカ本土への撤退論など、様々な提言がなされてきた。そしてその声を伝え続けてきたのは、琉球新報や沖縄タイムスである。つまり、通信社や全国メディアのワシントン特派員の配信記事の後追いなどではなく(というか、在米日本大使館ベッタリのワシントン特派員たちほど当てにならない存在はない。いや、彼らこそ日本のジャーナリズムを駄目にしている元凶だと厳しく指摘すべきでさえある)、自前の取材で、真実を明らかにし続けてきたのだ。
これを全国メディアのほとんどが無視し続けてきた実態がある。
これでは、沖縄とヤマト(日本本土)の住民の意識のギャップは広がるばかりである。
それどころか、実現不可能な計画を最善とうそぶく悪名高きケビン・メア元国務省日本部長(沖縄総領事経験者)の著書が売れて、日本の官僚・政治家が大いに影響を受けているらしいなんて話(永田町・霞が関の事情通の話・・・笑)を聞いた日には、まさに開いた口がふさがらない、というしかないわけであった。ケビン・メア君が辺野古新基地建設に固執するのは、彼自身がその計画を強硬に推進した直接の担当者だったからにすぎない。「努力(はっきり言って無駄な努力)」が水泡に帰するのが惜しいだけなのだ。
何はともあれ、沖縄のメディアは、早くから「普天間基地の辺野古移設」なる計画の欺瞞性を見抜き、様々な角度から検証を繰り返してきた。それらの報道に接してきたわたしは、辺野古新基地建設は、実現不可能である、と当ブログでも何度も断言してきた。
そしていよいよ、皮肉なことに、米国の側で「辺野古断念」の動きが加速してきているのである。
全国の皆さんには、今こそ、「辺野古移設が最善」などと繰り返している日本政府のおバカさ加減に気づいてほしい。
そのためには、情報の共有は欠かせない。
真実を伝えようとしない全国メディアはこの際ほうっておいて、沖縄のメディアに常に目を向けていただきたい。
その際に助けになるブログ・ホームページは多々あるけれど、まずはその代表例として、「地元紙で識るオキナワ」というブログを紹介しておこう。ぜひご注目ください。
→http://michisan.ti-da.net/
はじめての方には、遡っていろいろな記事をチェックされることをお勧めしたい。
さて、本日はこれから、八重山教科書問題の行政訴訟の第一回公判の傍聴へ、那覇地裁へ赴きたいと思っている。
本当は、「普天間問題」に関して、もう少しまとまったリポートを書きたいのだが、きょうはこのへんでご勘弁を。
これ以上ブログ更新が滞ることは避けたくて、取り急ぎ記事をアップしました。言葉足らずをご寛容ください。
※それから、改めてのお知らせです。
先にも告知させていただきましたが、『世界』2月号の拙文「与那国島に自衛隊は必要か(上)」の続編、すなわち(下)は、4月号掲載へ変更ですので、何とぞよろしくお願いします。(おそらく3月号は本日東京などで発売されたはずですので)
沖縄は、数日ごとに寒波到来、冷え込んでます。
皆さま体調崩されませぬように。では、また。
Posted by watanatsu at 08:40
│時事問題