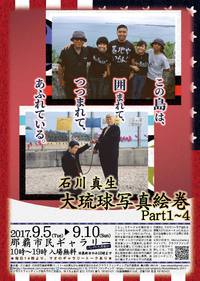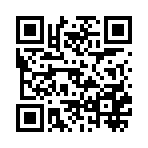2013年01月26日
『生きているということは』…常盤新平さんに捧ぐ。
別の場所にも書かせていただいたが、わたしにとって恩人の作家・常盤新平さんが亡くなったのは、1月22日の夜のことである。
asahi.comより引用(2013年1月22日22時35分の記事)http://www.asahi.com/obituaries/update/0122/TKY201301220376.html?tr=pc
↓↓↓
作家・常盤新平さん死去 「遠いアメリカ」で直木賞
直木賞作家で、アメリカの現代文学を紹介してきた翻訳家の常盤新平(ときわ・しんぺい)さんが、22日午後7時12分、肺炎のため東京都町田市の病院で死去した。81歳だった。葬儀は近親者で行う。喪主は妻陽子さん。
岩手県生まれ。早川書房に入社し、ミステリー小説誌「ハヤカワ・ミステリマガジン」の編集長を務めた。退社後に文筆生活に入り、自伝的小説「遠いアメリカ」で、1987年に第96回直木賞を受賞した。主な翻訳書にアーウィン・ショーの「夏服を着た女たち」など。ウォーターゲート事件の内幕を描いた「大統領の陰謀」も翻訳した。
*
その夜、たまたまわたしはFacebook友達がアップしてくれているこの動画に気づき、視聴して、しみじみとしていた。
上條恒彦が歌う『生きているということは』。
→http://www.youtube.com/watch?v=rW_AN3igKks
この動画を観て聴いて、それから間もなく、別件の調べものをするためネットでニュースを検索したとき、偶然にも常盤新平さんの訃報に接したのである。
常盤さんは、私の初めての著作『銀の夢 オグリキャップに賭けた人々』が講談社文庫におさめられたとき、巻末の解説文を書いてくださった方である。

その数年前にアメリカはケンタッキー州の牧場地帯からニューヨークへと旅をともにさせていただいたときの思い出を交えて、過分な励ましのエッセイを寄せて下さったのである。
あの頃、しばしば酒席をともにさせていただいた。
人生の先輩風を吹かせるようなこともなく、現代アメリカの文学や文化に関する当方の素朴な質問に対して、面倒くさがらずに丁寧に答えて下さったものである。
折にふれての常盤さんのご教示が、物書きになろうと心に決めつつあった20代の終わりから30代前半にかけてのわたしにとって、大いなる刺激となったことは言うまでもない。厳密に言えば、お付き合いを始めた頃のわたしの主な仕事は「雑誌編集者」としてのそれであった。若手編集者としてのわたしが、翻訳家としての長年の実績がある上に直木賞受賞作家としてますます脚光を浴びている常盤さんと、どんな面白い仕事をしようかと企み、語り合う、そのことに重きが置かれていたわけである。「常盤新平の世界の競馬紀行」が、当面の目玉企画であったが、その企画を認めてくれた雑誌は、間もなく休刊の憂き目にあい、企画自体が白紙に戻ってしまった。
当然と言うべきだろうか、「編集者」としてのわたしが常盤さんとお会いする頻度は減っていき、やがて、わたしはライターの道へと一歩踏み出すことになった。そうしてわたしが本を書いたとき、常盤さんは心から喜んでくださった。励ましてくださった。受賞もわが事のように祝ってくださった。
自著の文庫本の解説文を書くようにわたしを指名してくださったこともある。「これも励ましの一種だなぁ」と痛感したものだ。
しかし、わたしはまだ、その励ましの言葉に応えることができていない。
お世話になったまま、恩返しができていない。
三日前に訃報に接したとき、ただただそのような思いに包まれ、途方に暮れてしまった。
東京から遠く離れた沖縄へ移り住んでからは、お会いする機会がほとんどなくなってしまっていた。
この間、わたしはいったい何をしていたというのだ…。
そんな思いを抱えながら、もう一度、この歌を聴いた。
ますます胸に沁みこんできた。
いわゆる「六八コンビ」の歌だった。ある年齢以上の方には説明不要の作詞・作曲の名コンビである。
*
永六輔・作詞 中村八大・作曲
生きているということは
生きているということは
誰かに借りをつくること
生きていくということは
その借りを返してゆくこと
誰かに借りたら 誰かに返そう
誰かにそうして貰ったように
誰かにそうしてあげよう
生きていくということは
誰かと手をつなぐこと
つないだ手のぬくもりを
忘れないでいること
めぐり逢い 愛しあい
やがて別れの日
そのときに悔やまないように
今日を明日を生きよう
人は一人では生きてゆけない
誰も一人では歩いてゆけない
生きているということは
誰かに借りをつくること
生きていくということは
その借りを返してゆくこと
誰かに借りたら
誰かに返そう
誰かにそうして貰ったように
誰かにそうしてあげよう
誰かにそうしてあげよう
誰かにそうしてあげよう
*
偶然にしては出来すぎのようなタイミングでこの歌を教えてくれたFacebook友達のRさん、ありがとうございます。
不思議な気持ちです。
生きていくことで、これからの生き方で、恩返しをするしかない。
わたしは、今、己にそう言い聞かせています。
人生の折り返し地点をすでに過ぎ、決して先の長くない人生の時間。
しかしこれ以上悔やまないように、今日を明日を生きよう。
心の底からそう思うのです。
常盤新平さん、出会ってくださって、本当にありがとうございました。
どうぞ安らかにお休みください。
改めて……合掌。
asahi.comより引用(2013年1月22日22時35分の記事)http://www.asahi.com/obituaries/update/0122/TKY201301220376.html?tr=pc
↓↓↓
作家・常盤新平さん死去 「遠いアメリカ」で直木賞
直木賞作家で、アメリカの現代文学を紹介してきた翻訳家の常盤新平(ときわ・しんぺい)さんが、22日午後7時12分、肺炎のため東京都町田市の病院で死去した。81歳だった。葬儀は近親者で行う。喪主は妻陽子さん。
岩手県生まれ。早川書房に入社し、ミステリー小説誌「ハヤカワ・ミステリマガジン」の編集長を務めた。退社後に文筆生活に入り、自伝的小説「遠いアメリカ」で、1987年に第96回直木賞を受賞した。主な翻訳書にアーウィン・ショーの「夏服を着た女たち」など。ウォーターゲート事件の内幕を描いた「大統領の陰謀」も翻訳した。
*
その夜、たまたまわたしはFacebook友達がアップしてくれているこの動画に気づき、視聴して、しみじみとしていた。
上條恒彦が歌う『生きているということは』。
→http://www.youtube.com/watch?v=rW_AN3igKks
この動画を観て聴いて、それから間もなく、別件の調べものをするためネットでニュースを検索したとき、偶然にも常盤新平さんの訃報に接したのである。
常盤さんは、私の初めての著作『銀の夢 オグリキャップに賭けた人々』が講談社文庫におさめられたとき、巻末の解説文を書いてくださった方である。

その数年前にアメリカはケンタッキー州の牧場地帯からニューヨークへと旅をともにさせていただいたときの思い出を交えて、過分な励ましのエッセイを寄せて下さったのである。
あの頃、しばしば酒席をともにさせていただいた。
人生の先輩風を吹かせるようなこともなく、現代アメリカの文学や文化に関する当方の素朴な質問に対して、面倒くさがらずに丁寧に答えて下さったものである。
折にふれての常盤さんのご教示が、物書きになろうと心に決めつつあった20代の終わりから30代前半にかけてのわたしにとって、大いなる刺激となったことは言うまでもない。厳密に言えば、お付き合いを始めた頃のわたしの主な仕事は「雑誌編集者」としてのそれであった。若手編集者としてのわたしが、翻訳家としての長年の実績がある上に直木賞受賞作家としてますます脚光を浴びている常盤さんと、どんな面白い仕事をしようかと企み、語り合う、そのことに重きが置かれていたわけである。「常盤新平の世界の競馬紀行」が、当面の目玉企画であったが、その企画を認めてくれた雑誌は、間もなく休刊の憂き目にあい、企画自体が白紙に戻ってしまった。
当然と言うべきだろうか、「編集者」としてのわたしが常盤さんとお会いする頻度は減っていき、やがて、わたしはライターの道へと一歩踏み出すことになった。そうしてわたしが本を書いたとき、常盤さんは心から喜んでくださった。励ましてくださった。受賞もわが事のように祝ってくださった。
自著の文庫本の解説文を書くようにわたしを指名してくださったこともある。「これも励ましの一種だなぁ」と痛感したものだ。
しかし、わたしはまだ、その励ましの言葉に応えることができていない。
お世話になったまま、恩返しができていない。
三日前に訃報に接したとき、ただただそのような思いに包まれ、途方に暮れてしまった。
東京から遠く離れた沖縄へ移り住んでからは、お会いする機会がほとんどなくなってしまっていた。
この間、わたしはいったい何をしていたというのだ…。
そんな思いを抱えながら、もう一度、この歌を聴いた。
ますます胸に沁みこんできた。
いわゆる「六八コンビ」の歌だった。ある年齢以上の方には説明不要の作詞・作曲の名コンビである。
*
永六輔・作詞 中村八大・作曲
生きているということは
生きているということは
誰かに借りをつくること
生きていくということは
その借りを返してゆくこと
誰かに借りたら 誰かに返そう
誰かにそうして貰ったように
誰かにそうしてあげよう
生きていくということは
誰かと手をつなぐこと
つないだ手のぬくもりを
忘れないでいること
めぐり逢い 愛しあい
やがて別れの日
そのときに悔やまないように
今日を明日を生きよう
人は一人では生きてゆけない
誰も一人では歩いてゆけない
生きているということは
誰かに借りをつくること
生きていくということは
その借りを返してゆくこと
誰かに借りたら
誰かに返そう
誰かにそうして貰ったように
誰かにそうしてあげよう
誰かにそうしてあげよう
誰かにそうしてあげよう
*
偶然にしては出来すぎのようなタイミングでこの歌を教えてくれたFacebook友達のRさん、ありがとうございます。
不思議な気持ちです。
生きていくことで、これからの生き方で、恩返しをするしかない。
わたしは、今、己にそう言い聞かせています。
人生の折り返し地点をすでに過ぎ、決して先の長くない人生の時間。
しかしこれ以上悔やまないように、今日を明日を生きよう。
心の底からそう思うのです。
常盤新平さん、出会ってくださって、本当にありがとうございました。
どうぞ安らかにお休みください。
改めて……合掌。
Posted by watanatsu at 04:38
│哀悼