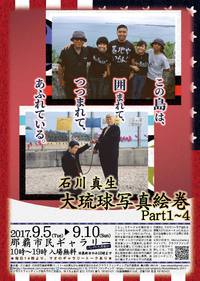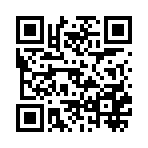2013年09月15日
沖縄と福島を切り捨てて、繁栄を謳歌したいかニッポン人!!
不思議なことに、いま突然眼前に、3ヵ月近くも前の朝日新聞の社説が立ち現れた。
沖縄の「慰霊の日」の翌日の社説である。
かなり、まともだ。
読売や産経の稚拙な差別的暴論に負けるなよ。3.11以後の東京新聞の姿勢を見習えよ。
そうだ、朝日新聞、本気で頑張れよ。頑張ってくれ!!
そう思ったので、ここに全文引用紹介する次第。
【沖縄慰霊の日 戦争の教訓共有しよう】 2013.6.24.朝日新聞・社説
本土の目に映る沖縄は、沖縄の人々が真に見てほしい姿だろうか。それとも、本土が自分の都合で描く沖縄だろうか。
きのう「慰霊の日」を迎えた沖縄と本土との間に最近、ひときわ意識のずれが目立つ。
たとえば普天間飛行場問題。県外移設を訴える沖縄の声に、本土はもはや聞く耳をもたぬかのようだ。参院選の公約で自民党本部は、県連の反対を押し切り、辺野古移設を明記した。
4月に政府が催した「主権回復の日」式典をめぐっては、沖縄は米施政下に置き去りにされた「屈辱の日」と抗議した。一方、オスプレイ配備の本土分散は遅々として進んでいない。
沖縄から見る本土への心の距離は開くばかりだ。ところが皮肉にも、人々が国家主権を語るとき、沖縄はがぜん、本土の意識の中で重い存在感を担う。
中国共産党の機関紙が、沖縄における日本の主権は未解決とする論文を掲載すると、日本政府はただちに抗議した。中国への国民の憤りは当然だ。
だが、「領土」「安保」の文脈では日本人の自尊心を映す国土であるのに、沖縄県民の目線に立つ「地元」の声は本土に届かない。そんな本土と沖縄を分かつ溝の原点を、わたしたちは常に熟考する必要がある。
最大の悲劇は太平洋戦争末期の沖縄戦だった。68年前、本土防衛を前に、戦略上の捨て石とされた沖縄は、地上戦の修羅場と化した。
「鉄の暴風」といわれた米軍の砲撃や空襲。日本兵に殺されたり、集団死を強いられたりした地元民もいた。死者20万。県民の4人に1人が落命した。
あの戦場をくぐった高齢者の4割が今も、心にストレス障害を患っている可能性が高いとの調査結果を、沖縄の研究者たちが今春まとめた。不発弾や遺骨は今も日常的に見つかり、米兵の犯罪もあとを絶たない。
「戦争」は沖縄の人々の中では、今も終わっていないのだ。なのに、本土はその思いを共有しないどころか、軍事基地の重荷を沖縄に過剰に背負わせたまま、憲法改正による「国防軍」創設まで語り始めている。
きのうの追悼式で、沖縄県の仲井真弘多知事は、癒えることのない痛みにふれつつ、「私たちは沖縄戦の教訓を継承する」と誓った。日本の戦後の安定と繁栄は何を犠牲にして築かれたのか。その教訓を沖縄だけのものにしてはならない。
「慰霊の日」を機に、いま一度、沖縄戦の記憶を直視しよう。沖縄と本土の意識のずれを少しでも修正するために。
*
この社説に出てくる「沖縄の研究者」とは、わたしのよく知っている蟻塚亮二さん(福島県相馬市のメンタルクリニックなごみ所長、前沖縄協同病院心療内科部長、)や當山冨士子さん(元沖縄県立看護大学教授)たちのことだ。
実名をあげて紹介し論じてもよい「沖縄戦PTSD」の具体的な研究成果があるのだが、まずは社説でそのことに触れただけでもよしとしよう。
意識のズレは、何も沖縄と「本土」との間にだけあるのではない。
「東京オリンピック招致活動→開催決定」で浮かれ放題の人びとと、福島第一原発放射能被災者をはじめ震災被災地の復興を望む人びととの意識のズレは、深刻な問題を今後7年間にわたって、鮮明に浮き彫りにするに違いない。
いまこそ、沖縄の現実を視よ、福島の現実を視よ!! 目をそらすな。
話はそれからなのだ。
沖縄と福島からは、この国の狂った姿がよく見える。
自他ともに認めるスポーツ好きのわたしとて、東京五輪をもろ手をあげて歓迎するわけには決していかないのである。
沖縄の「慰霊の日」の翌日の社説である。
かなり、まともだ。
読売や産経の稚拙な差別的暴論に負けるなよ。3.11以後の東京新聞の姿勢を見習えよ。
そうだ、朝日新聞、本気で頑張れよ。頑張ってくれ!!
そう思ったので、ここに全文引用紹介する次第。
【沖縄慰霊の日 戦争の教訓共有しよう】 2013.6.24.朝日新聞・社説
本土の目に映る沖縄は、沖縄の人々が真に見てほしい姿だろうか。それとも、本土が自分の都合で描く沖縄だろうか。
きのう「慰霊の日」を迎えた沖縄と本土との間に最近、ひときわ意識のずれが目立つ。
たとえば普天間飛行場問題。県外移設を訴える沖縄の声に、本土はもはや聞く耳をもたぬかのようだ。参院選の公約で自民党本部は、県連の反対を押し切り、辺野古移設を明記した。
4月に政府が催した「主権回復の日」式典をめぐっては、沖縄は米施政下に置き去りにされた「屈辱の日」と抗議した。一方、オスプレイ配備の本土分散は遅々として進んでいない。
沖縄から見る本土への心の距離は開くばかりだ。ところが皮肉にも、人々が国家主権を語るとき、沖縄はがぜん、本土の意識の中で重い存在感を担う。
中国共産党の機関紙が、沖縄における日本の主権は未解決とする論文を掲載すると、日本政府はただちに抗議した。中国への国民の憤りは当然だ。
だが、「領土」「安保」の文脈では日本人の自尊心を映す国土であるのに、沖縄県民の目線に立つ「地元」の声は本土に届かない。そんな本土と沖縄を分かつ溝の原点を、わたしたちは常に熟考する必要がある。
最大の悲劇は太平洋戦争末期の沖縄戦だった。68年前、本土防衛を前に、戦略上の捨て石とされた沖縄は、地上戦の修羅場と化した。
「鉄の暴風」といわれた米軍の砲撃や空襲。日本兵に殺されたり、集団死を強いられたりした地元民もいた。死者20万。県民の4人に1人が落命した。
あの戦場をくぐった高齢者の4割が今も、心にストレス障害を患っている可能性が高いとの調査結果を、沖縄の研究者たちが今春まとめた。不発弾や遺骨は今も日常的に見つかり、米兵の犯罪もあとを絶たない。
「戦争」は沖縄の人々の中では、今も終わっていないのだ。なのに、本土はその思いを共有しないどころか、軍事基地の重荷を沖縄に過剰に背負わせたまま、憲法改正による「国防軍」創設まで語り始めている。
きのうの追悼式で、沖縄県の仲井真弘多知事は、癒えることのない痛みにふれつつ、「私たちは沖縄戦の教訓を継承する」と誓った。日本の戦後の安定と繁栄は何を犠牲にして築かれたのか。その教訓を沖縄だけのものにしてはならない。
「慰霊の日」を機に、いま一度、沖縄戦の記憶を直視しよう。沖縄と本土の意識のずれを少しでも修正するために。
*
この社説に出てくる「沖縄の研究者」とは、わたしのよく知っている蟻塚亮二さん(福島県相馬市のメンタルクリニックなごみ所長、前沖縄協同病院心療内科部長、)や當山冨士子さん(元沖縄県立看護大学教授)たちのことだ。
実名をあげて紹介し論じてもよい「沖縄戦PTSD」の具体的な研究成果があるのだが、まずは社説でそのことに触れただけでもよしとしよう。
意識のズレは、何も沖縄と「本土」との間にだけあるのではない。
「東京オリンピック招致活動→開催決定」で浮かれ放題の人びとと、福島第一原発放射能被災者をはじめ震災被災地の復興を望む人びととの意識のズレは、深刻な問題を今後7年間にわたって、鮮明に浮き彫りにするに違いない。
いまこそ、沖縄の現実を視よ、福島の現実を視よ!! 目をそらすな。
話はそれからなのだ。
沖縄と福島からは、この国の狂った姿がよく見える。
自他ともに認めるスポーツ好きのわたしとて、東京五輪をもろ手をあげて歓迎するわけには決していかないのである。
Posted by watanatsu at 02:09
│時事問題